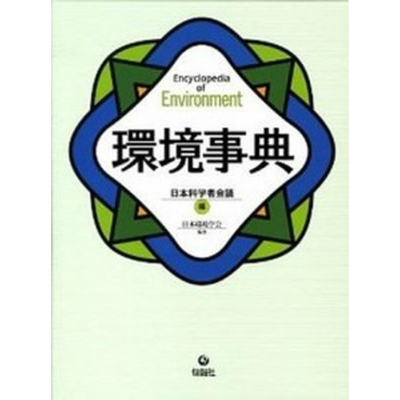| 用語 | 説明 |
|---|---|
| HEP-NEP | HEPは「人間特例主義パラダイム(Human Exemptionalism Paradigm)」、NEPは「新エコロジカルパラダイム(New Ecological paradigm)」の略語。1970年代、環境問題を社会現象として捉えて分析した研究が盛んになり、こうした「環境問題の社会学」をめぐってアメリカで論争が生じた。キャットン(W. Catton)とダンラップ(R. Dunlap)は、従来の社会学が自然環境とのかかわりに無関心であったことを指摘し、人間は社会的・文化的な環境からの影響が決定的であり自然界では特例的な存在であると考える「人間特例主義パラダイム(HEP)」を批判した。そして、人間も地球上に生存する無数の生物種のひとつに過ぎず、エコロジーの法則を超えられないという「新エコロジカルパラダイム(NEP)」への転換を提唱し、いわゆるHEP-NEP論争を展開した。こうした伝統的な社会学に対する根源的な批判から、1970年代後半にアメリカで環境社会学が誕生した。 |
| アソシエーション | ある特定の関心や目的を共通に持つ人びとが作る組織化された集団。マッキーバー(MacIver, R. M.)の古典的なコミュニティ論の影響により、しばしばコミュニティと対照的な概念として理解される。マッキーバーは、地域社会をコミュニティとアソシエーションとに分類し、前者が地域性と共同性とに基礎づけられる生活体であるのに対し、後者はコミュニティを母体として、特定の機能に基づいた組織体であると整理した。しかし、こうした分類にもかかわらず、地域環境の保全を目的とて自発的に活動するボランティア団体やNGO・NPOは、コミュニティと呼ばれることが多い。この理由としては、地域環境問題を解決する場合であっても、そうした特定の目的だけではなく、地域社会の生活を豊かにする必要性を認識しているから、機能体としてのアソシエーションではなく、生活体としてのコミュニティが選ばれると分析されている。 |
| 新しいコモンズ | 地縁を超えて人びとが共同で資源を管理する制度、あるいは共同管理の対象となる資源。伝統的なコモンズでは、地縁による地元住民の集まりが管理主体であったのに対して、新しいコモンズでは都市住民など地域を超えて人びとが資源を管理する。人と自然の関係性が希薄化して生物多様性が失われている一方で、自発的に里山などの管理活動にかかわるボランティアが増えており、これを新しいコモンズの胎動として評価する向きがある。 |
| エリート主義的環境主義 | 環境を守ろうとする思想のうち、社会のなかで権力と影響力を持つ少数者集団に特徴的な考え方。環境破壊の原因が主として支配者層にある一方で、その被害が低所得者層や社会的弱者に偏っているという環境的不公正を問題にする概念。エリート層は環境を保全しようという意識が相対的に高いものの、環境破壊を引き起こす社会の不公正をないがしろにしたままで、環境問題の原因がどこにあるのかを隠蔽しているという批判を含んでいる。 |
| 援農 | 地縁や血縁ではなく自発的に農作業を手伝うこと。有機農業運動のなかで、農産物の生産状況を理解し、労働力不足を補うために、消費者が農作業を手伝ったことから全国に広がった。今日、余暇活動としての農作業に関心が高まっており、農地を有効活用するとともに、市民の余暇の充実と農業への理解を深める機会として、自治体や農協などが積極的に推進している。労働の対価を求めず、無償ボランティアとして作業する場合が多い。 |
| オゴニ生存運動 | ニジェール・デルタの先住民であるオゴニ(Ogoni)が、自分たちの土地(オゴニランド)の権利を守り、環境破壊に抗議するために提起した運動団体。1958年から石油メジャーのシェル社はオゴニランドで油田の採掘を始めたが、オゴニに対して収益を配分・還元しないばかりか、原油流出などによる環境破壊を引き起こした。1990年、作家のケン・サロ=ウィワ(Kenule Saro-Wiwa)らは非暴力の抗議運動を開始し、1993年にはオゴニの総人口の半数が結集するまでに拡大した。シェル社はオゴニランドでの操業を停止したが、ナイジェリア軍事政権はサロ=ウィワら運動の指導者を逮捕し、1995年に処刑した。 |
| 小樽のまちづくり | 運河保存運動とその後の展開のなかで、小樽の住民が地域社会に住むことを問い直してきた一連の動き。小樽市が地域のシンボルであった運河を埋め立てる工事を始めた着手したことに対して、1973年に地域住民は「小樽運河を守る会」を組織し、計画の凍結保存を訴えた。1977年以降は、歴史的町並み保存運動の全国的な広がりを背景に、運河という小樽に固有の環境に学ぶべきと主張するなど、新しい考えを提案しながら支持者を増やしていった。住民側は運河の埋め立て幅を半分に減らす譲歩案を引き出したが、さらなる譲歩を求めて組織の拡大を図ったところ内部分裂を起こし、1986年に運河の半分は埋め立てられた。12年にわたる運河保存運動の効果として、小樽は知名度を挙げて北海道を代表する観光地となった。一方、住民側には、運河を観光資源とするのではなく、運河とともに住む生活を守りたかったことに気づき、小樽に住む意味を深く問い直す動きが生じた。 |
| 加害型ジレンマ | 環境問題における社会的ジレンマのうち、受益圏と受苦圏が分離しているタイプ。舩橋晴俊は、社会的ジレンマが原因となって生じる典型例として環境問題を把握したうえで、受益圏と受苦圏の重なり具合によって、自己回帰型、格差自損型、加害型の3つに分類した。加害型ジレンマとしては、工場排水による水質汚濁、高速道路公害、放射性廃棄物問題などがあり、いずれもほぼ一方的に利益を得る主体がほかの主体に損害を与える。 |
| 格差自損型ジレンマ | 環境問題における社会的ジレンマのうち、受益圏と受苦圏がほぼ重なりつつも、利益を得る者と損害を被る者の間に格差をともなうタイプ。舩橋晴俊は、社会的ジレンマが原因となって生じる典型例として環境問題を把握したうえで、受益圏と受苦圏の重なり具合によって、自己回帰型、格差自損型、加害型の3つに分類した。格差自損型ジレンマとしては、地盤沈下、自動車排気ガス公害、清掃工場建設問題などがある。 |
| 嘉田由紀子(1950-) | 鳥越皓之らとともに生活環境主義を唱える環境社会学者。1976年に琵琶湖周辺で人間と生活環境のかかわりについて本格的な調査を始めてから、同じ所で長期にわたり徹底したフィールドワークをおこなってきた。アフリカやアジアの湖と琵琶湖との比較研究もある。1981年に琵琶湖研究所に入ってからは、市民参加による身近な水環境調査を実施したほか、1996年に開館した琵琶湖博物館には構想段階から深く関わった。2006年7月から滋賀県知事。 |
| 鎌倉古都保存地区 | 「古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法」(通称「古都保存法」)に基づき、日本固有の歴史的風土を継承するために指定された鎌倉市内の区域。1964年、鶴岡八幡宮の裏山における宅地造成計画に対し地元住民を中心に反対運動が起こり、大佛次郎など鎌倉在住の多くの著名人も参加した。鎌倉市のほかに京都市や奈良市でも古都保存運動が盛んになり、世論に後押しされるかたちで1966年に古都保存法が制定された。 |
| 環境共存 | 人間と環境が相互作用するシステムにおいて、持続的な安定性が認められること。あるいは、人間と環境の関係性が好ましいこと。この環境とは、主として自然環境を指すが、町並みなどの歴史的・文化的環境でもよい。環境問題が社会的に構築されることを気にせず、いささか乱暴に、環境問題の反対語として説明されることもある。また、環境共存という美名のもとに、人びとの生活に制約を加え、変更を迫るような政策に注意が必要である。 |
| 環境共存の社会学 | 環境共存の事例を扱いながら、人間と環境が相互作用する持続的なシステムの様態や、人びとが抱く価値観などを研究する環境社会学の分野。研究対象領域の違いから、環境問題の社会学の対義語として用いられることが多い。さまざまな時代や地域において、環境と調和して暮らしている、あるいは暮らしてきた社会の事例を調査し、ときには通時的・共時的に比較しながら、環境問題の解決法や環境共存の可能性などを検討する。 |
| 環境行動の社会学 | 環境への負荷を軽減しようとする日常的な行動から、健康被害を受けた人びとによる反公害運動にいたるまで、行動レベルに焦点を当てて研究する環境社会学の分野。行動レベルではなく、価値意識のレベルを研究する場合は、環境意識・環境文化の社会学と呼ばれる。人間と環境の関係性を改善しようとする環境行動において、人びとが出会う困難や障害やその克服のされ方、環境運動が生じる契機や効果などについて研究する。 |
| 環境社会学 | 人間社会とそれを取り巻く環境との相互関係について、社会的側面に注目して研究する社会学。環境社会学という名称は、1970年代にダンラップ(R. Dunlap)などアメリカの社会学者の間で公的に使用され始めた。日本での環境社会学的な研究は1950年代半ばから農村社会学者や地域社会学者によって始まっており、実質的にはアメリカよりも早い時期からなされている。日本で最初の環境社会学的研究とされるのは、島崎稔らによる安中鉱害問題の調査研究であり、1960年代半ばには福武直による四日市公害の社会学的研究もおこなわれている。こうした研究に、社会運動論、都市社会学、保健社会学、科学・技術論などの専門家による公害・環境問題の研究が加わって、次第に環境社会学の形が整えられてきた。そして、1995年には環境社会学会が発足し、標準的なテキストが相次いで刊行されるなど、近年、学問としての制度化が急速に進んだ。研究対象領域を大別すると、<環境問題の社会学>と<環境共存の社会学>の2つに分けられる。<環境問題の社会学>では、環境問題が作り出される社会的しくみ(加害構造)や、問題によって被害を受ける人びとの特徴や被害が広がるしくみ(被害構造)などを研究する。<環境共存の社会学>では、自然と調和して暮らしてきた地域社会に埋め込まれているしくみや、自然環境やコミュニティを再生しようとする動きなどを研究する。これまでの理論的な成果としては、飯島伸子が公害・環境問題の社会史研究などから形成した加害-被害構造論、舩橋晴俊や長谷川公一らが新幹線公害の研究などから形成した受益圏・受苦圏論、海野道郎がごみ問題の研究から形成した社会的ジレンマ論、鳥越皓之や嘉田由紀子らが琵琶湖周辺の村落調査から形成した生活環境主義などが知られている。このほかに、構築主義、リスク社会論、コモンズ論、環境ガバナンス論、エコロジカル・モダニゼーション論の研究なども盛んである。 |
| 環境社会学会 | 「環境社会学の研究に携わる者による研究成果の発表と相互交流を通して、環境に関わる社会科学の発展および環境問題の解決に貢献すること」を目的とした学会。1990年5月に前身の環境社会学研究会が発足し、1992年10月にこれが発展的に改組されて環境社会学会が設立された。毎年2回、春と秋にセミナーを開催して研究報告やシンポジウムをおこなうほか、春はフィールド・トリップも実施して、現地関係者との情報交換・交流により地域環境問題の実態把握に努めている。これまでに、水俣、阿賀野川、足尾銅山、白神山地、沖縄の基地問題の現場などを訪ねてきた。1995年からは、この分野の学術的研究の発展に貢献するとともに、環境問題に関心を持つ多様な分野との研究交流や意見交換の場となることをめざして、学会誌『環境社会学研究』を年に1回発行している。これは、世界で初めての環境社会学の専門誌と言われている。現在、会員数は400名を越えている。 |
| 環境人種差別 | 環境汚染の被害や迷惑施設の立地などが、被差別集団の有色人種や少数民族に集中すること。貧困層への差別なども含め、環境差別と総称される。1980年代後半から、多民族国家であるアメリカにおいて、有害廃棄物の処理施設がアフリカ系黒人の多く住む地域に集中していると実証されるなど、環境負荷が人種によって不平等に分配されている事実が相次いで報告された。これに対し、人種や民族、職業や所得などと関係なく、環境汚染や健康被害から保護されるべきという信念から、環境差別を是正する環境正義運動が広がった。連邦政府は、国民の関心の高まりを受けて、1992年、環境保護庁に環境正義局を開設した。さらに1994年2月には、当時のクリントン大統領が「環境正義に関する大統領令」を出し、連邦政府機関が事業を実施する際には、人種的マイノリティや貧困層の環境や健康に不利な影響を及ぼさないかを把握し、適切に対応するように示された。 |
| 環境保全 | 人間が手を加えながら環境を適切に管理すること。環境思想では、保存(preservation)と保全(conservation)を区別する伝統がある。すなわち保存とは、自然それ自体に貴重な価値があると考え、人間による攪乱からできるだけ保護しようとすることである。一方の保存とは、適切に自然を管理しないと人間の側に被害が及ぶと考え、人びとの福祉を維持・拡大するために資源を賢明に管理・利用することである。保存と保全の考え方が鋭く対立した例として、ヨセミテ国立公園内にあるヘッチヘッチー渓谷のダム建設をめぐる論争が有名である。アメリカ最初の自然保護団体シエラ・クラブ(Sierra Club)を設立したミューア(J. Muir)は、原生的な自然を守るためにダムの建設に反対したのに対し、森林局の初代長官を務めたピンショー(G. Pinshot)は、サンフランシスコの慢性的な水不足の解消と水力発電による電力確保という功利主義的な考えからダムの建設に賛成した。 |
| 観光開発 | 観光振興によって地域開発をおこなうこと。多くの観光振興が地域の社会と環境に大きな影響を及ぼすので、環境問題への関心が高い現代社会では、観光開発による環境への影響が問題となる。特に大衆的な観光(mass tourism)では、開発にともなう環境破壊が深刻な問題となりやすいことから、将来世代も観光資源を享受できるように、適切に管理しながら利用していく持続可能な観光(sustainable tourism)を模索する動きがある。 |
| キーパースン | 重要人物、中心人物。たとえば、環境運動やまちづくり活動では、運動や活動の理念を唱えるリーダーや優れた調整役などであり、展開の過程を理解する上で鍵となるような人。しばしば、フィールドワークによって事例調査をすすめる場合、キーパーソンへの聞き取りが不可欠になる。環境社会学的には、キーパーソンの社会的な働きを見きわめるとともに、彼(女)の行為や価値観などを社会的な相互作用から説明する必要がある。 |
| 機能主義 | ある社会的事象を、ほかの活動や制度、あるいは社会全体の動きにどう影響するかという観点からとらえようとする立場。社会システムの安定性をマクロな視点から分析する際に、高い説明力を持つとされていた。1970年代以降、ミクロな社会関係に関心が高まる中で、機能主義は個人が自身の行為に与えている意味を把握できないという批判などを受け、社会を統一的に説明しようとする議論は下火になっている。 |
| 近自然型工法 | 工事によって影響を受ける自然生態系について、その復元・保全・創出をめざす工法。1970年代、破壊された生態系を復元する工法として、スイスやドイツで誕生した。河川改修や森林整備の手法として、また都市の基盤整備にも応用されている。この工法では、水際や林縁部など異なる生態系が接する境界領域(エコトーン)を重視するので、そこに多様な生物種が出現するとともに、それぞれの生態系は独立性を保つことができる。1980年代なかばに日本に紹介されたが、近自然という言葉がわかりにくかったため多自然型工法と呼ばれることが多い。 |
| クラインガルテン | ドイツ語で「小さな庭」を意味する滞在型の市民農園。19世紀はじめにドイツのライプチヒ市において、土地と仕事のない市民に与えられた救貧農園が起源とされている。ドイツでは、ラウベ(laube)と呼ばれる簡易宿泊施設が併設されており、そこに滞在しながら菜園づくりを楽しむとともに、地域住民とも交流できる。クラインガルテン協会が管理し、希望者は協会員になって区画を借りる。日本でも、都市と農村の交流を目的に、農村地域で宿泊施設をともなう農園の整備が進んでいる。 |
| グリーン電力運動 | 風力や太陽光、バイオマス、小規模水力などの自然エネルギーによって発電された電力を、消費者が選んで購入できるようにすすめる運動。1990年代はじめにアメリカで消費者運動として始まり、欧米を中心に拡大している。日本では、1999年に電力料金の5%分を基金として風力発電所を設置する運動が始まり、2000年からは、グリーン電力の環境上の価値をグリーン電力証書として発行し、環境対策の一環として取引するしくみも始まった。 |
| 原因論 | 原因についての議論。環境問題に限定すれば、その問題を引き起こした原因を突きとめようとするもの。環境問題を社会学的に分析する研究は、加害論・原因論、被害論、解決論の3つに分けることができる。原因論は、加害論とならんで加害者側に焦点を当てて、どのような行為の積み重ねから加害が生じたのか、どのような社会のメカニズムによって加害行為が放置・拡大されたのかなど、環境問題の原因を解明しようとする。 |
| 原子力資料情報室 | 故・高木仁三郎を中心として、原子力に依存しない社会をめざして1975年に設立され、1999年にNPO法人化した民間の調査研究機関。産業界とは独立した立場から、原子力に関する各種資料の収集や調査研究などをおこない、市民に役立つように情報を提供している。高木仁三郎は、日本における脱原発運動のリーダーであったのと同時に、市民がさまざまな現場から学び、自ら問題に取り組む市民科学の提唱者としても知られる。 |
| 構造化された選択肢 | いくつかの選択肢から自由に選べるように見えて、実は選択できる範囲が社会的に限定/決定されている状況。個人の行為が社会の構造によって決まる側面を指摘する概念である。たとえば、環境問題の解決にはライフスタイルの変革が必要と言われることがあるが、環境破壊型の社会システムが放置されたままでは個人の選択を変えることは難しい。このように、個人的な問題と思われることを社会的な問題として捉える直すときに用いられる。 |
| 古都保存法 | 「古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法」の略称。日本固有の文化的遺産として、今後とも継承していくべき古都の歴史的風土を保全するために制定された法律である。古都を保存するために必要なところを歴史的風土保存区域に指定し、域内における建築物の新築等については知事への許可あるいは届出を必要とするなど開発が規制される。また、その土地の所有者に対しては救済措置として、損失補償および買取り請求に基づく土地の買い入れ制度を定めている。この法律が適用されるのは、京都府の京都市、神奈川県の鎌倉市、逗子市、奈良県の奈良市、天理市、橿原市、桜井市、斑鳩町、明日香村、滋賀県大津市である。1960年頃から古都周辺で宅地造成などによる都市化が進展し、歴史ある風土が破壊されつつあった。この問題に対して、鎌倉市などで古都保存運動が盛り上がり、議員立法によって1966年に制定された。 |
| 産直運動 | 産直とは生産者と消費者が生鮮食料品を直接取引することで、産直運動はこれを推進する社会運動のこと。1960年代、既存の流通制度に対抗して卸売市場を経由せずに購入する消費者運動として始まり、その後は新鮮で安全な食を求める人びとによって支えられてきた。取扱量で産直の中心的役割を担っている生協では、産直を単なる「産地直送」ではなく、生産者と消費者の顔が見える「産地直結」の活動として位置づけている。そして、産直3原則として、1)生産地と生産者が明確であること、2)栽培・肥育方法(農薬・肥料・飼育など)が明確であること、3)組合員と生産者が交流できること、を掲げている。 |
| 自然環境主義 | 人間の手が加わらない原生的な自然を望ましいと考える立場。生活環境主義者が環境思想としてのエコロジーを想定して定義した。自然環境主義では、重視すべき点は人間の生活ではなく自然環境に置かれるので、人間は自然の一部だとみなされる。生活環境主義は、この自然に対する人間の関与を拒否する自然環境主義と、近代的な技術を適用すれば環境問題は解決できるとする近代技術主義を、ともに批判するなかから考え出された。 |
| 社会的景観 | 目に見える景色のとらえ方が、見る者の生きる社会から規定されること。普通、景観とは建物や緑などを指し、同じ景色は誰にでも同様に映るとみなされるが、社会的と修飾されたときには、同じ景色を眺めても地域や時代によって感じ方が異なるように、見え方が社会から影響を受けていることを強調する。なお景観を、森林・河川などの自然景観と都市・農地などの文化景観に分けることがあり、後者を社会的景観と呼ぶこともある。 |
| 集合財 | 社会集団全体に利益をもたらし、非排除性と競合性を持つ財。一例として公園が挙げられる。まず、公園は誰でも利用することができ、特定の利用者を排除しないという意味で非排除性を持つ。そして、利用者が少なければ競合しないものの、多くの人びとが利用するときには快適性が減少するという意味で競合性を持つので集合財に含まれる。経済学者のオルソン(M. Olson)が、灯台のような非排除性と非競合性を備えた公共財と区別するために定義して以来、公共性をめぐる議論などで広く用いられている概念である。オルソンによれば、利己的な個人は集合財を自分に都合よく利用するだけで、それを維持するために必要なコストを負担しないフリーライダー(ただ乗り)になりやすく、また、この問題は集団の規模が大きいほど生じやすい。環境社会学における社会的ジレンマ論では、この考えを環境問題に適用し、環境破壊の原因は少ない集合財をめぐる競合にあるとする。 |
| 状況の定義 | 人がある場面に出会ったとき、一貫した方法で選択して知覚し、解釈すること。つまり、人は視野に入るものをすべて等しく認識するのではなく、その場面が自分にとってどのような状況であるのかを選択的に認識して解釈するのである。地域の環境問題をめぐって行政と住民との間で話し合いの場が設けられても、何が問題なのか、それをいかに解決すべきなのかなどの点において、双方の状況の定義がずれていると議論がすれ違ってしまう。 |
| 人工的自然 | 人間が手を加えることによって形成された自然。一般に自然の対義語として人工があるが、この場合の自然は人為が加えられていない原生自然を意味しており、実際には人間と自然との相互作用が認められることが多い。日本の人工的自然の代表は、雑木林、人工林、農地などによって構成される里地里山であろう。この空間は高い生物多様性を誇るとともに、ローカル・ナレッジが蓄積されてきた場としても注目される。 |
| 身土不二 | 人間の身体と土地は二つではない、すなわち一体であるという言葉で、身近なところで育ったものを食べるのが身体によいという考え方。1890年代頃から石塚左玄らによって始まった自然食運動(食養道運動)のなかで、仏教用語にあった身土不二(しんどふに)を借用してスローガンとして使われたことで広まった。近年では、スローフード運動や地産地消運動の標語として用いられることがある。 |
| 新マルサス主義 | イギリスの経済学者マルサス(Malthus, T. R.)の理論にならい、人口増加は環境問題のような社会問題をもたらすとして人口の抑制を唱える考え方。マルサスは、人口が等比級数的に増えるのに対して、食糧は等差級数的にしか増産できないので、将来的に貧困などの深刻な社会問題が生じると主張した。この議論を再現するように、1972年にローマクラブが発表した報告書『成長の限界』では、地球の有限性を指摘して人類の活動を制限するように提言した。 |
| スモール・イズ・ビューティフル | 1973年、イギリスの経済学者シューマッハー(Schumacher E. F.)が著したエッセイ集の題名、あるいは彼が将来のあるべき価値観を表現した標語。大きいことや大きいものを良いと考えるのではなく、人間の身の丈に合う適当な小さいことや小さいものを美しいと捉える価値観を意味する。シューマッハーは、著書『スモール・イズ・ビューティフル』のなかで、環境破壊の現状を直視し、インドやミャンマーを訪問した経験をもとにして、現代文明の根底にある物質至上主義と科学技術の巨大信仰を批判した。そして、将来の展望として、自然資本を枯渇させるのではなく持続的に利用する適正技術、または伝統技術と先端技術の中道をめざす中間技術を重視した開発の必要性を説いた。2001年、文化人類学者の辻信一がこの言葉をいかして『スロー・イズ・ビューティフル』を著し、早さを要求される現代社会にあって、遅さとしての文化を見直す社会運動が広がった。 |
| 生活環境主義 | 環境を保護するうえで、居住者の生活を保全することが最も重要であると考える立場。欧米のモデルの焼き直しではなく、日本の環境社会学研究が琵琶湖の総合開発紛争の現場から生み出した。代表的な論者としては、鳥越皓之や嘉田由紀子を挙げることができる。この理論的立場が誕生した1970年代後半~80年代にかけては、環境問題を解決するための主要な考え方が2つあった。1つは生態学の理論を借用し、健全な生態系を守ることをよしとするエコロジー論であり、もう1つは近代技術が最終的に問題を解決するという考え方であった。生活環境主義者は、前者を自然環境主義、後者を近代技術主義と呼び、両者とも異なる考え方・立場として生活環境主義を位置づけ、生活のために必要な地域社会の資源やしくみを保守することが大切であると主張した。生活環境主義では基本理論として、所有論、権力論(意思決定論)、組織論(主体性論)を用意している。所有論は、明治以降の近代法が土地の私有権を強固に認めてきた結果、しばしば環境保全に対して負の機能を果たしているという認識から出発している。法律分野において環境権を認めさせようとする運動が十分な効果を示すことができないなかで、実証的な社会学的研究から、土地を所有していなくても、人びとがその場所に働きかけることによって結果的に占有してしまう共同占有というあり方を示した。一方、権力論(意思決定論)は、人びとが運動のなかで容易に自分の意見を変える事実を素朴に否定するのではなく、「言い分」が構成員の間でどのように正当性を持つようになったのかに注目する。また組織論は、住民がしばしば組織を分裂させてしまうという課題から議論されたものである。生活環境主義では、居住民を把握しなければ、その地域環境を守るために有効な方策を検討できないと考えるので、地域社会に住む人びとの生活の経験や歴史の分析が重要な位置を占める。 |
| 生活クラブ生協 | 生活協同組合のひとつであり、独自の厳しい基準で食料・日用雑貨・衣料などを共同購入することで知られる。1965年、生活クラブとして牛乳の共同購入を始め、1968年に生活クラブ生協が設立された。共同購入品は、利潤追求を目的としないで使用価値を重視する観点から、商品ではなく消費材と呼ばれている。また、生活者とは消費するだけではなく、日常の暮らしのなかで意識的に生活のあり方を考えていく存在であると位置づけ、生活者にふさわしく身体に安全で環境に配慮したものを取り扱ってきた。 |
| 生活権 | 人びとが健康で文化的な生活を営む権利。これが侵されると、生活そのものが成立しなくなるもので、生活者の基本的人権として位置づけられる。日本の歴史をひもとけば、人びとは生活するために土地に働きかける(たとえば耕す)ことで、その場所を所有していなくても占有する権利(たとえば耕作権)を得てきた。所有と利用を切り離して捉えるコモンズ論によれば、コモンズは社会的な弱者の生活権を保障する機能を持っている。 |
| 生活史研究 | ある個人に焦点を定め、生涯を通じて取り巻く社会を探る質的研究。口述の聞き取りのほか、自伝、日記の収集などによって、個人の生活史を明らかにする。生活史研究は、個人の主観性を分析するさいに社会構造へと還元してきた社会学的な研究方法に対する批判から生まれ、社会学のほか、人類学、民俗学、歴史学などでも盛んである。なお自然科学では、生物の一生にわたる変化を、その生活に即して明らかにする研究を指す。 |
| 生活システム | 生活のための利用を前提とした土地、用水、公民館、年中行事、常識などの資源を基盤にして成立している地域社会のしくみ。生活環境主義では、居住者の生活環境を保護することが重要と考えるが、このとき保守すべき対象とは生活システムにほかならない。なお、パーソンズ(T. Parsons)の社会システム論にならって定義されることもあり、この場合は生活者の意識と行動と構造が相互に関係しながら生活が維持されるしくみを意味する。 |
| 生活者の加害者化 | 日常生活に由来する環境問題への関心が高まり、生活者が環境に与える負の影響の広がりや深まりを重視した言い方。典型的な公害では、相対的に力のある国、地方自治体、企業などが加害者となり、生活者は被害者になることが一般的だった。これに対して、大量生産・大量消費・大量廃棄を前提する社会では、人びとの日常生活の積み重ねによって環境問題が引き起こされると理解され、生活者を加害者として認識する見方が浸透してきた。 |
| 生活知 | 人びとの生活に根ざし、人が充実した生を送るために必要な知。類義語としては、経験知、日常知、暗黙知などがある。専門家による普遍的な知識である科学知(あるいは、専門知、世界知など)と対照的な意味を持ち、地域性が現れやすい智恵である。しかし、生活知と科学知は相反するものではない。生活者は、さまざまな科学知のなかから特定のものを適当に選択して、日常生活に位置づけながら状況の解釈をおこなう。 |
| 生活の質 | 人が人間らしく充実感や満足感を持って生活を送っているのか、その質を計る尺度として働く概念。おもに医療や福祉の歴史とともに発展し、重視されるようになってきた。背景としては、患者や要介護者の自己決定が尊重されるようになってきたことや、慢性的な医療や介護を必要とすることが増え、疾病や傷害を抱えつつも尊厳を保って生きることが求められるようになってきたことを挙げられる。また、それまで医療や福祉が医者や介護者の視点から評価されてきたことに対して、患者や要介護者の視点からこそ評価すべきという考え方を反映したものともいえる。一方、この概念は開発の分野でも重視されるようになっている。経済的な発展を目標とした開発事業によって、人びとの生活環境がかえって破壊されるという例が目立つようになり、安心して日常生活を営めることや持続的に生計を確保できることなどに重きを置いて住民の暮らしが評価されるようになっている。 |
| 生活文化 | 日常の生活を営むときの方法や様式。家庭や地域社会などの生活の場における行事や衣食住にまつわる文化などである。生活の質を豊かにするうえで重要と考える向きがある。音楽、絵画、演劇などと比較して、芸術文化としての自律した領域を形成していない領域という側面もある。しかし、日常生活から生まれた文化的行動が洗練されて芸術文化になることもあるので、歴史的・社会的な文脈に置かれてみて、はじめて指示することができる。 |
| 生活防衛型運動 | 人びとが自分の生活を保守するためにおこなう社会運動。図式的に整理すると、住民運動は直接的な利害関係者である地域住民により自らの生活を守る運動であり、市民運動は良心的な市民による普遍的な価値を守るための運動となる。したがって、生活防衛型運動とは住民運動型の環境運動と重なる部分が多い。日本の環境運動は、生活防衛のための運動から、防衛すべき生活の破壊を予防する運動へと成熟してきたと言われる。 |
| 生活由来の環境問題 | 大量に生産・消費・廃棄することを前提とした社会にあって、日常生活が引き起こす環境問題で、自動車の排気ガス問題や騒音などが挙げられる。加害者と被害者が明確な理念的な公害と異なり、生活由来の環境問題では解決論が不十分と言われている。個人の主体性を強調する場合はライフスタイルの転換をめざし、社会構造の問題を重視する場合はその変革を求めるが、現実の解決過程は複雑なので、こうした考えだけでは説明が難しい。 |
| 世界システム論 | 地球規模の経済システムである資本主義について、起源と展開を歴史的に明らかにして、その性質を把握しようとする理論。ウォーラーステイン(I. Wallerstein)によって提唱された。世界システム論によれば、現代の資本主義は国家の枠組みを超えてグローバルに展開しており、このなかには経済的・政治的に支配的な中核地域と、これに従属する周辺地域がある。1990年代以降、グローバル化という広い概念のなかで議論されることが多い。 |
| 石けん運動 | 合成洗剤の使用をやめて、粉石けんを使おうとする社会運動。1977年5月、琵琶湖に悪臭を放つ淡水赤)が大発生し、その原因のひとつが、合成洗剤に含まれているリンにあることがわかった。この赤潮の発生をきっかけとして、滋賀県内の消費者団体など県民が主体となり、リンを含む合成洗剤の使用をやめて天然油脂を主原料とした粉石けんを使おうという運動が始まり、急速に広がった。この動きを受けて1980年7月には、リンを含む家庭用合成洗剤の販売・使用の禁止、窒素やリンの工場排水規制を盛り込んだ「滋賀県琵琶湖の富栄養化の防止に関する条例」(通称「琵琶湖条例」)が施行された。運動は全国的な注目を集めて合成洗剤からリンが除かれたが、無リン合成洗剤の登場などによって粉石けんの使用率は低下した。石けん運動で回収していた廃食用油の行き場が狭められたので、これを有効活用する手法としてバイオディーゼル燃料化が登場した。 |
| 戦争遺産 | 戦争のために造られた要塞、砲台などの遺構や、戦災で被害を受けた建物などで、戦時をものがたる遺物として歴史的な価値のあるもの。軍事遺産とも言う。アウシュヴィッツ=ビルケナウ強制収容所や原爆ドームなどが有名であり、負の歴史的遺産と重なることが多い。日本では負の記憶を呼び覚ますので積極的には保存されてこなかったが、1980年代半ばから調査や保存運動などがおこなわれ、その価値が認められるようになってきた。 |
| 総有 | ある財産が団体の所有となっており、その財産が団体によって強く拘束されている状態であること。団体財産が総有であるときは、各構成員には持分がないので分割できないし、各構成員は団体から脱退する際に、持分の払い戻しを受けられない。日本の入会がコモンズの悲劇を招かず、自然資源が持続的に共同利用されてきた理由として、地域共同体がその山林原野等を総有しており、各人の行為が厳しく制限されたことが挙げられる。 |
| 第五福竜丸 | 1954年3月1日、マーシャル諸島近海において操業中に、ビキニ環礁で行われたアメリカの水爆実験によって被災したマグロ漁船。放射性降下物(死の灰)によって船員23名全員が被曝し、半年後に無線長の久保山愛吉さんが亡くなった。実験当時、第五福竜丸のほかにも多くの漁船が周辺で操業しており、2万人近くが被曝したとみられている。現在は、東京都江東区にある都立第五福竜丸展示館に保存されている。 |
| ダンラップ(1943-) | 1970年代後半に環境社会学の誕生に尽力したアメリカの社会学者。農村社会学者だったダンラップは、従来の社会学が人間を自然界で特別な存在とみなす「人間特例主義パラダイム(HEP)」を採用してきたと批判し、人間もエコロジーの法則を超えられないという「新エコロジカルパラダイム(NEP)」への転換を提唱した。環境社会学は、このHEP-NEP論争のなかから産声を上げた。現在は、オクラホマ州立大学で教鞭を執っている。 |
| 地域エゴ | 公共のために必要な事業であることを理解しつつ、それによって利益が生じる場合は自分の居住地域でおこなわれることに賛成し、損害が生じる場合には反対するという住民の利己的な姿勢を揶揄した言葉。ごみ焼却場や廃棄物処分場などの迷惑施設の建設に際し、反対する地域住民を指して言うことが多い。しかし、地域エゴに見える問題の背景には、受益圏と受苦圏が乖離しているために被害が局所に集中する事実が隠れていることもある。 |
| 地域おこし | 基礎自治体である市町村や、それよりも範囲の狭い地区において、経済や文化の活性化をはかること。地域振興や地域活性化よりも語感の柔らかい表現を用いることにより、行政、住民、商工会、農協、学校など地元の人びとの主体性が強調される。基幹産業の衰退によって雇用機会が減少したり、利便性において近隣地域との格差が拡大したりすると、地域経済が縮小して人口も流出するが、こうした問題を克服するための活動が地域おこしである。企業の誘致、美術館・博物館などの建設、地場産品の開発、イベントの新設など、多様な試みがなされてきたが、どの地域でも有効な解決策はない。地域の立地、人口や産業の構造、さらにその地域の特徴を判断し、独自性のある事業が必要となる。近年は、新しい地域おこしの考え方として地元学が提唱され、恵まれた環境や伝統技術などの地域資源を見つめ直し、それを生かして住民が幸せに暮らせる地域づくりも模索されている。 |
| 地域環境主義 | 個人的な環境と地球規模の環境のあいだにある地域環境という単位を立脚点として環境問題をとらえていこうとする立場。飯島伸子が廃棄物問題の調査研究を進めるなかで定義した。1990年頃から地球環境の危機が声高に叫ばれる方向で世論が進みつつあったことと、地球環境の改善策を論じる際に自治体・企業・NPOなどを含む地域社会の問題を飛ばして、個人の責任に還元する言説が支配的であったことから、この概念が必要と考えられた。 |
| 地域共同管理論 | 地域社会における住民は生活をまっとうするために地域そのものを管理するが、この行為は既存の地域秩序を維持・統合するだけではなく、自治を通して主体が形成されるとダイナミックに捉える考え方。社会学者の中田実によって提唱された。地域住民が共同で管理する対象は、土地や施設設備、景観、行事や社会関係などであるが、共同管理の基盤は、定住生活の空間的な受け皿であり、住民生活のための資源提供の場である土地とされる。 |
| 伝統文化 | 長い歴史のなかで人々に受け継がれてきた文化で、一般には、歌舞伎、茶道、着物などがイメージされる。しかし、伝統とは創られるものであるとする社会学的な見方からすれば、伝統文化とは近代化の中で見出されるものであり、客観的にはさほど古くなくても主観的に古く見える現象である。このように定義は困難であるので、何が伝統文化であるのかを問うよりも、伝統文化とされるものが果たしている機能に着目することが生産的である。 |
| 都市社会学 | 都市や都市化をおもな対象とする社会学。1920~30年代、シカゴ学派と呼ばれる研究者集団によって実証的な研究が本格的に始まった。その後、コミュニティを対象とした研究が盛んになり、多数の優れたエスノグラフィーが書かれた。1970年代以降、都市をジェンダーや階級などの切り口から権力の現れる場として捉える新都市社会学が登場し、国家における位置関係や社会運動との関わりなどから都市を捉える視点が重視されてきた。 |
| ナワシステム | ヒマラヤ山麓に住むシェルパ族の社会に埋め込まれた環境保全のしくみ。ナワには、森林の伐採を管理するナワと、ヤクなどの家畜の移動を管理するナワがあった。ところが、観光客が増大して森林破壊が危惧されるようになり、ヤクのナワは廃止され、森のナワは森林保護管が担当することになった。シェルパの人びとは、この近代的な森林管理制度を生活しやすいように換骨奪胎したものの、資源を収奪しなかったことが知られている。 |
| 人間の鎖 | 政治的な抗議行動の手段として、多くの人びとが手をつないで連帯を示すデモンストレーション。たとえば、1989年にバルト三国(エストニア、ラトビア、リトアニア)独立運動の一環としてつくられた人間の鎖は、約200万人が参加して3カ国を結び、600km以上の人間の鎖(別名「バルトの道」)を形成した。反核運動や反基地運動では、しばしば原子力発電所や軍事基地などを取り囲む。 |
| 比較優位の原則 | 国際貿易では、各国がすべての財を自国内で自給自足するよりも、他国と比べて有効に生産できる産業に特化しつつ他の財を輸入する方が、限りある資源のもとで多くの財を利用できるという原則。国際的な自由貿易を推進する立場から、しばしば引き合いに出される。理論的には、経済学者のリカード(Ricardo, D.)が、他国より生産性が低くても、少ない機会費用で生産できる比較優位な財ならば、国際的な競争力を持つことを説明した。 |
| 非紛争型の環境問題 | 被害者が加害者を告訴する公害裁判のような争いを伴わない環境問題で、生活排水問題やごみ問題などが挙げられる。こうした生活由来の環境問題では、加害者と被害者とを単純に区別できないので、何を問題とすべきで、どのように解決すべきなのかも確定しないことが多い。それでも、問題に直面している人びとは、先の展望が見えないなかで解決策を模索しているのが現状で、こうした状況を分析できる概念枠組みが必要とされている。 |
| 不可視の権力作用 | 自分が見えないところから監視されているかのように、常に自己を律していくことで、結果として社会の秩序が維持される力の働き。フーコー(M. Foucault)は、一人ひとりが自己監視する規律訓育型権力を描くことで、それまでの権力のとらえ方を大きく変えた。つまり、超越的な者の持つ抑圧的な力が見えるため権力が働くと捉えるのではなく、権力が不可視で非人称的であるから自己の規律化によって効力が発揮されると捉えた。 |
| 不可知論 | 感覚的な経験を超えたものを人間は知りえないとする立場。神の存在に関しては、神が実在するかどうかは認識できないと考えるので、有神論と無神論のどちらの立場も取ることができる。ヒューム(D. Hume)は、人間の認識がもっぱら印象と観念で成り立っているため、客観的実在があるかどうか知ることはできないとする。カント(I. Kant)は、意識の外に物自体が存在することを承認するが、その本当の姿を人間は認識できないと考える。 |
| 負の歴史的遺産 | 戦災や公害などの悲惨な記憶をとどめている歴史的な建造物など。広島の原爆ドームのような戦争遺産のほか、環境汚染や労働災害をもたらした跡地、旧植民地時代の建築物など、近現代史の否定的側面を示す遺産を指す。こうした建造物の保存は、負の記憶を喚起するので多くの論議を呼ぶ。なぜなら、忌まわしい過去を早く忘れたいので早く撤去すべきという考えと、だからこそ人類の遺産として残すべきという2通りの考えを生むからである。 |
| 文化的環境 | 言語や習慣、生活様式など人間社会の象徴的・習得的な環境。または、町並みや遺跡などの歴史的文化財や伝統文化。あるいは、文化的な生活を営むために必要な日照や静穏など。空気や水などの自然環境とは違って人間社会に固有の環境であるが、社会的環境という用語では指し示すことが難しいようなものを広く指す。したがって、文化的という言葉が「文化の」「(正統な)文化の」「文化的な」と解釈され、多義的な用語になっている。 |
| 保健社会学 | 健康・病気と保健・医療をめぐる問題群を対象とする社会学。近年では、健康が損なわれる要因や、病気から回復し、健康を保持・増進できたりする条件に、その人が置かれている社会的な環境が大きく影響していることが指摘されている。また、健康が単に身体的に異常な症状があるかどうかという状態を指すのではなく、精神的にも社会的にも良い状態であることが求められており、保健社会学が対象とする領域はますます広がっている。 |
| マクロ的視点/ミクロ的視点 | 社会現象を把握するうえで、個人のパーソナリティーや対人関係などに着目する視点をミクロ的、社会構造や文化体系や社会変動などに注目する視点をマクロ的と呼ぶ。巨視的視点/微視的視点ともいう。もともとは、近代経済学で確立された2つの分析視角であるが、社会学では、ミクロ分析とマクロ分析との関係性がうまくつながるわけではない。なお、組織や制度に注目する場合を、メゾレベルの視点と呼ぶこともある。 |
| まちづくり運動 | 地域社会の多様な主体が連携し、地域の資源を生かしながら身近な環境を良くすることで、まちとしての価値を高めていく持続的な活動。町や街ではなく平仮名の「まち」を用いることで、行政が住民の意向と関わりなく施設整備するという活性化方策とは異なるイメージを生みだしている。つまり、手法としてはハードよりもソフトの面を強調し、主体は住民が担うか、住民と行政との協働によって推進されるものとして捉えられることが多い。 |
| 村しごと | 村で生きていくために人がおこなうべき役割だと考えられているもので、たとえば畑仕事や山仕事がある。これらは、村の人びとが暮らす地域の環境を守ることにつながっている。また、一人暮らしの高齢者の具合が悪くなったとき、村人が共同で助け合うことなども含まれる。哲学者の内山節によれば、山村では「仕事」と「稼ぎ」が日常的に区別されており、「稼ぎ」は貨幣を稼ぐためにする労働を意味するという。 |
| やすらぎ主義 | 地域社会では、構成員全員の幸福(welfare)や安らぎ(feel at home)を保障することが必要であるという考え。環境社会学者の鳥越皓之は、伝統的な地域コミュニティと近代化の過程で新しく形成しようとするコミュニティが構成員に与える共通の特長として安らぎを見いだした。コミュニティを重視する立場からすると、安らぎは人間が生きていくうえで重要であるのに、機能が特定化されたアソシエーションでは供給できないと考える。 |
| 吉野山 | 奈良県の中央部にある標高455mの山。一帯は1936年に吉野熊野国立公園に指定され、2004年には「紀伊山地の霊場と参詣道」としてユネスコの世界遺産に登録された。古くから花の名所として有名だが、サクラに覆われる吉野山の景観は、平安時代の頃から人びとが植え続けた結果であり、人工の自然ともいえる。従来の信仰、観光のほか、近年では環境保全の観点からもサクラを守ろうという動きがあり、社会学的な分析対象となっている。 |
| よそ者 | ほかの土地から移って来た人。環境運動では、地域住民以外の人が支援しに来ても、よそ者と呼ばれて、当該地域の現状を理解しない者として否定的に扱われることがあった。しかし、環境倫理学者の鬼頭秀一は、諫早湾や奄美大島の自然の権利訴訟において、よそ者と地元が互いに学び合いながら両者の視点を持つことで、運動が展開していったことを肯定的に評価した。また、まちづくりの手法の1つである地元学でも、地元がよそ者とともに地域資源を発見することが重視されている。 |
| 歴史的環境 | 長期間にわたって保存され、歴史上または芸術上、一定の価値を持つと評価されるもの。そして、一つひとつの物件の価値ではなく、それらが集合することによって生じるまとまりから地域固有の歴史を感じさせるものを言う。土地の歴史、人びとの記憶が刻まれた景観、遺跡、町並みなど有形物のほか、伝統芸能のような無形のものも含まれる。日本では1969年の新全国総合開発計画において公的に用いられ、1970年代以降、この用語が頻繁に用いられるようになった。歴史的環境保全の系譜をたどると、歴史的文化財の対象や範疇を拡大してきた流れと、まちづくり運動の一環として取り組まれてきた生活環境保全の流れがある。歴史的環境の価値は、保存されてきた時間の長さだけで決まるのではなく、対象に対する人びとの思いの強さや深さも関係する。つまり、郷愁、記憶、思い出などを多く人びとに喚起させるものは、価値が高いものと認識される。 |
| 歴史的町並み保存運動 | 歴史的な建造物の保存や修景を通じて、地域に固有の歴史や文化などを総合的に整備し、まちづくりをすすめていく社会運動。高度経済成長期に古い建物が壊されていくなかで、長野県妻籠宿で町並みを守る運動が始まり、この動きが全国に展開していった。1975年に文化財保護法が改正され、伝統的建造物群保存地区の制度が誕生したことにより、城下町、宿場町、門前町など伝統的な町並み・集落の保存が図られるようになった。 |
| ローカル・コモンズ | コモンズを、自然資源をある構成員が共同で利用・管理する制度、および共同管理の対象である資源それ自体と定義したとき、これが地域社会程度の範囲で成立するもの。したがって入会のように、自然資源にアクセスできる権利は一定の社会集団に限定される。これに対して、グローバル・コモンズ(Global Commons)とは地球規模で成立するコモンズであるから、自然資源にアクセスできる権利は一定の社会集団に限定されない。 |
| ローカルな知 | 特定の地域社会に見られる固有な知識。文化人類学者のギアーツ(C. Geertz)が論文の題名にしたことから広まった概念。専門家の科学的知識と対照的に、普通の人びとが持っている経験的・実践的な智恵として用いられる。実際、先住民の伝統的・生態学的知識は専門家もかなわないことが多い。1980年代以降、近代的な科学技術による開発手法に限界が見え始め、ローカルな知を持続可能な開発のために役立てようとする研究が盛んである。 |
松村正治(2008)「HEP-NEP」「アソシエーション」「新しいコモンズ」「エリート主義的環境主義」「縁農」「オゴニ生存運動」「小樽のまちづくり」「加害型ジレンマ」「格差自損型ジレンマ」「嘉田由紀子」「鎌倉古都保存地区」「環境共存」「環境共存の社会学」「環境行動の社会学」「環境社会学」「環境社会学会」「環境人種差別」「環境保全」「観光開発」「キーパースン」「機能主義」「近自然型工法」「クライン・ガルテン」「グリーン電力運動」「原因論」「原子力資料情報室」「構造化された選択肢」「古都保存法」「産直運動」「自然環境主義」「社会的景観」「集合財」「状況の定義」「人工的自然」「身土不二」「新マルサス主義」「スモール・イズ・ビューティフル」「生活環境主義」「生活クラブ生協」「生活権」「生活史研究」「生活システム」「生活者の加害者化」「生活知」「生活の質」「生活文化」「生活防衛型運動」「生活由来の環境問題」「世界システム論」「石けん運動」「戦争遺産」「総有」「第五福竜丸」「ダンラップ」「地域エゴ」「地域おこし」「地域環境主義」「地域共同管理論」「伝統文化」「都市社会学」「ナワシステム」「人間の鎖」「比較優位の原則」「非紛争型の環境問題」「不可視の権力作用」「不可知論」「負の歴史的遺産」「文化的環境」「保健社会学」「マクロ的視点・ミクロ的視点」「まちづくり運動」「村しごと」「やすらぎ主義」「吉野山」「よそもの」「歴史的環境」「歴史的町並み保存運動」「ローカルコモンズ」「ローカルな知」日本科学者会議編『環境事典』旬報社.