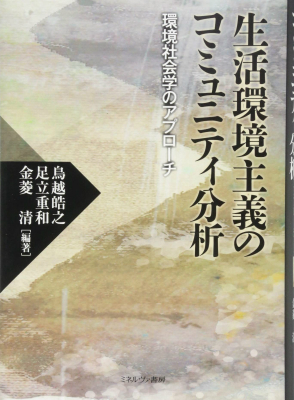経験と感受性から生活環境主義を読み直す―鳥越皓之・足立重和・金菱清編『生活環境主義のコミュニティ分析』を読んで
1.はじめに
1.1. 私と鳥越スクール
本書は、鳥越皓之さんの退官記念論文集である。書籍販売サイトの説明によれば、「鳥越に薫陶を受けた論者たちが、それぞれのフィールドとの格闘から生活環境主義という立場の現代的な意義を新たに見出す」ために刊行された。鳥越門下生24人による論考が収められており、500ページを優に超える大部である。まずは、この記念碑的労作の評者として、編者からご指名いただいたことを光栄に思い、素直に喜びたい。
さて、学会誌上では、本稿と編者によるリプライがセットになって掲載されるだろうが、私と鳥越スクールとの対話は今回が初めてではない。個人的なことになるがふりかえっておくと、最初は2002年9月の環境社会学会研究例会であった。当時、2001年度~02年度の研究例会では、「環境社会学の主要な研究諸潮流の回顧的検討」をテーマとして、学会設立後10年間の研究を総括し、諸概念の再検討が試みられた。そのなかで生活環境主義について検討する研究会があり、私は「『生活環境主義』以降の環境社会学のために」と題して報告をおこない、荒川康さんが生活環境主義を擁護する立場から応戦した。その後、このときの議論をもとに私はレビュー論文をまとめ、荒川さんは五十川飛暁さんと共著論文を発表した(松村, 2007, 荒川・五十川, 2008)。
その拙論は読まれることの少ない科研費報告書に収められたので、鳥越さんから読まれた感想をメールでいただいたときには驚いた。さらに、その後ほどなくして、テキスト『よくわかる環境社会学』に「生活環境主義」について1ページで説明するコラムの執筆を依頼された。鳥越スクールの門下生ならば、生活環境主義をめぐる豊富な議論の蓄積を考慮して、この仕事は無理難題だと考えたに違いにない。私はせっかくいただいた機会だからと引き受けたものの、脱稿後、自分が書いてよかったのだろうかと考え続けたし、それは今も変わっていない。
1.2. 本稿で議論すること
本書は、生活環境主義を理論的に再考する序章と、鳥越さんが生活環境主義のこれまでとこれからについて語る補論があり、あいだに個別の事例分析が5部24章に収められている。紙幅は限られており、すべてに公平にふれることは生産的ではないので、本稿では序章と補論から議論したい点を選び、適宜、その論点に関連する論考を取り上げる1。
私と鳥越スクールとの対話に関して、補論で以前書いた拙論が「生活環境主義の歴史的役割が終了したというような趣旨の論文」2として言及され、「松村さんの指摘は半分当たっていて、半分当たっていない」[p.530]と評されている。この評価に対しては応えたいので、論点の1つに生活環境主義は陳腐化したのか、を置く。
つぎに、力の入った序章の足立論文から2つの論点を取り出したい。1つは経験と感受性について、もう1つは現場との格闘と立場性について。それぞれ序章の3節と4節に対応する。
最後には、そうした議論を踏まえて本書の意義を考えたい。鳥越さんは門下生に対し、「各論者は事例を生活環境主義で書くことはできるので、それに簡単に甘んじることなく、生活環境主義を乗り越える」[p.538]ようにと注文されたそうだが、この点について私見を述べたい。
2.生活環境主義は陳腐化したのか
本書を通読したときの私の印象は、「環境社会学・地域社会学におけるオーソドックスな質的調査研究の論文集」であった。論文の水準にばらつきはあるものの、全体的には読み応えのある内容が多い。「オーソドックスな」という形容は、言葉のとおり、フィールドワークに基づく質的社会調査のなかで正統的と解したからである。たとえば、原発災害による放射能汚染の事例を扱う金子論文は問いの立て方が鋭いと感じるし、新旧住民を区別するルール設定に共在性の論理を見出す閻論文はユニークな事例が丁寧に描かれていて興味深く読ませる。
これらの論文を読む際、著者が生活環境主義に立っているかどうかを気にすることはなかった。ならば、生活環境主義を標榜することにどのような意味があるのだろうか。
今回、本書を読んで、生活環境主義の歴史的役割が終わったのかどうかをあらためて考えた。その結論は、以前の拙論に書いたときと変わらなかった。すなわち、政策論としては陳腐化したが、認識論としては依然として独自性を失っていないというものである。
ここで陳腐化とは、補論の見出しから引用したに過ぎず、マイナスには捉えていない。むしろ、目新しさがなくなり、ありふれて普通になったことは、ひとまずプラスに捉えるべきだろう。生活環境主義が提唱された1980年代は、環境問題に対応する考え方が自然環境主義と近代技術主義にほぼ限られていた。当時と比較すれば、環境政策を立案・運用する際、「当該社会に実際に生活する居住者の立場」に配慮するようになった部分は多いだろう。また、今日の福祉・防災・まちづくりなどの地域政策においては、コミュニティ単位の重要性が謳われ、居住者によりそうことがよしとされる。
もちろん、このような傾向は居住者への配慮が細やかになったことを意味しない。経済のグローバリゼーションや少子高齢化といった時代背景から、新自由主義的な地域政策が居住者の立場性に寄りかかる傾向を強めている面がある。また、住民を第一に考える政策が、見かけだけ言葉だけに終わるという問題も見逃せない。たとえば、金菱論文では、行政主導のレディーメイドな災害復興政策が住民不在のまちづくりに終わっているのに対し、住民が自分たちのためのオーダーメイドのまちづくりを実現できた事例を取り上げ、そうした復興を支える社会的条件を抽出している。五十川論文では、アンダーユースな河川敷のコモンズ空間において、地域の人びとがその空間をどのように認識し扱っているかを明らかにし、認識論に基づいた柔軟な政策論の必要性を主張している。どちらも、重要な指摘を含む政策論であるが、本稿ではここから認識論へと議論を移す。というのも、生活環境主義の政策論のベースは認識論にあると思われるからである。
3.人間として在ること―経験と感受性
生活環境主義の認識論において、人びとの行為ではなく経験を分析するという方法は今日でも魅力的である。序章と補論を読んで、この「経験」に対する私の理解は浅薄だったと感じた。補論で鳥越さんは、森有正の経験論から影響を受けたことを述べているが、この意味は重要である。
森の経験概念を理解するため、経験と体験と比較して論じている箇所を引用する。
人間はだれも『経験』をはなれては存在しない。……経験の中にあるものが過去的なものになったままで、現在に働きかけてくる。そのようなとき、私は体験というのです。/それに対して経験の内容が、絶えず新しいものによってこわされて、新しいものとして成立し直していくのが経験です。経験ということは、根本的に、未来へ向かって人間の存在が動いていく。一方、体験ということは、経験が、過去のある一つの特定の時点に凝固したようになってしまうことです。(森, 1970: 96-97)
森の経験論をもとに、生活環境主義を読み直すことができる。たとえば、生活環境主義では、容易に観察可能な表面的な行為ではなく、特定の行為が生成された経験のレベルまで降り立って見ていくと宣言するが、その経験とは静的な体験と違って動的なプロセスであることに気づかされる。さらに、生活環境主義では、人びとの語りの「豹変」を単なる気まぐれとして片付けない理由も理解できよう3。そうした経験こそが、「人間として在る」ことを保証しているからである。
足立論文では、生活環境主義が照準を定める経験について、行為としての「言い分」や「経験」の語りと「人びとの心=感受性」の関係を分析し、経験レベルの「深層的な言い分」から特定の「表層的な言い分」が語られるプロセスとその重層性に注意を促す。さらに、「経験」よりも経験に随伴する「感受性」を準拠点にして分析する重要性を提起する。
私には、この「経験論の解剖学」の論理が腑に落ちてはいない。それでも、生活環境主義を再考するなかで強調された感受性という言葉には惹かれた。私ならば、経験よりも感受性が大事だと言うのではなく、経験と感受性を相関する概念として措定してみたい。つまり、森の経験論を踏まえ、人びとにとって経験が絶えず更新されていくときには感受性を伴うこと、また、研究者が住民の経験を理解するときにも感受性を伴うこと。これらの関係性を、生活環境主義の経験論の内からつかみ取りたい。
私たち人間は、行為を通して得られた経験を次に生かそうと考える。そうした経験を重ねる人びとと感じ合い、互いに影響を受けながら、よりよく生きようと願う。生活環境主義では、感じないでブレない生き方を貫くことよりも、生活を組み立てるために柔軟に変化していく人びとの主体性に重きを置く。これは地域住民への信頼というよりも、人間の生に対する肯定感によって支えられているように思われるし、生活環境主義の独自性を際立たせる特徴だろうと考えている。
4.いったい誰の問題なのか―現場との格闘と立場性
すでに議論は次の論点へと移っている。足立論文では、研究者が「居住者の立場」に立つことは「心地よい」ように「よりそう」という生易しいものではなく、格闘の末に苦渋を伴いながら到達するものであると言う。ここに見られるいら立ちは、調査経験の長いベテラン研究者がフィールドワークの一般的な心構えを説いたものではない。地元住民の経験を見つめようと研ぎ澄ます感受性は、おのずと研究者本人の立場を不安にさせる。第三者的な客観的な視座から決まった視角で調査対象を捉えようとする立場は許されず、住民と同様に研究者もまた「人間として在る」ことがたえず問われる。それがフィールドワーカーの行く現場であろう。
そのような現場との格闘を経て、研究者が「居住者の立場」に立つことで目ざすことは、それまでよりも見通しよく社会を分析できる視点や視野の獲得である。この点から興味深く読んだ論考として、土屋論文と山室論文を挙げることができる。
土屋論文では、震災がれきという「負財」を誰が引き受けるのかというNIMBY問題について、Y市の事例分析を通して考察を深めている。「環境の安全性」をめぐり、地元の理解を求める行政と地元に連帯を呼びかける抗議運動とのはざまに地域住民は置かれ、不信と反目が増幅されてしまう可能性が生じる。住民は意向調査を実施して、地域社会の総意に委ねるという判断を下す。この事例に見られる住民の論理を追いながら、NIMBY問題では「どこかで誰かに引き受けさせなければならない問題」が、引き受けさせる側から引き受けさせられる側へと問題が転移されていく過程を明らかにし、小さなコミュニティ分析がこの問題の構造がどこにあるのかを照らし出す。
一方、山室論文では、JCO臨界事故後に原子力施設の周囲コミュニティが形成された事例を扱っている。「JCOから半径三五〇メートル内/外」および「反対/推進」という既存の二分法的カテゴリーに囚われず、住民有志が「周辺住民」としてJCOと敵対関係にならずに「住民と従業員の安全安心」を求めるコミュニティ形成に努めてきた。これは、原発城下町と化して損なわれやすい地域の自立性の向上と、立地点の生活保全につながっていくと言う。
これらの論文に迫力があるのは、「居住者の立場」に立って議論しているからに違いないのだが、その意味については、もう少し深く考えておきたい。もともと生活環境主義とは、環境問題が先にあり、この問題を考えるために生まれた。その際、「居住者の立場」に立つと決めたのは、この問題がいったい誰の問題なのかということを、突き詰めて考えたからであろう。それをコミュニティの問題であると言った場合、それは地域エゴであるとか、コミュニティの範囲はどこまでなのかという議論が続く。また、コミュニティの保全を大切にする論理に対して、外部者は地元住民に対して態度を明確にすること、争点を先鋭化することを求めがちである。しかし、土屋論文や山室論文からは、そうした議論が現代の地域社会では力を持たないことを示している。生活環境主義は「のどかで平和な日常生活世界論」と揶揄されることがあったが、これらの論文が示すように、賛成/反対が鋭く対立する環境問題の現場でこそ鋭い切れ味を見せる。さらに、現代社会における共同性や連帯の可能性について、現実的に考える材料を提供してくれるのだ。
研究者は問題を引き受けざるをえない居住者の立場から、考え抜くことが求められる。わかりやすい図式で解釈されることを拒む住民の主体的なふるまいを理解するには、研究者がそれまで持っていた認識枠組みを更新せざるをえない。そのとき、学問上に新しい発見がもたらされる。このような現場との格闘の末にようやく、「居住者の立場」に立つと言えるのであろう。
5.本書は生活環境主義を乗り越えたのか
最後に、本書は生活環境主義を乗り越えることができたのだろうか。鳥越さんの言葉にならえば、「半分は成功し、半分はそうとも言えない」と思う。
成功している点として、生活環境主義によって非常に幅広い対象が捉えられると示したことがある。それも、震災・復興、人口減少・少子高齢化といった現代的な社会課題を扱える強みを存分に発揮している。
成功しているとも言えない点として、興味深い事例分析が多く含まれているものの、それらの総合から生活環境主義の新しい像が立体的に見えて来なかったことがある。5部構成の本書は、各部のタイトルに生活環境主義の問いがあてがわれている。すなわち、「コミュニティはなぜ小さくなければならないのか」「コミュニティはなぜわれわれ意識を保持するのか」「コミュニティはなぜ分け合うのか」「コミュニティはなぜ存続しなければならないのか」「コミュニティはなぜ資源を利用しなければならないのか」。多くの論文は部のタイトルに引きつけて議論されているが、強引にかこつけたように感じられるものもあり、全体的には有効に機能していない。
鳥越スクールの論文は、一般に問題設定がシンプルで的確であるという印象がある。あとがきで金菱さんが鳥越ゼミの思い出を語っているが、「議論の焦点になったのは、ぎゅーっと真綿で首を締められても、それでも譲れない研究の一線はなんだろう」と繰り返し問い、絞り出された鋭さを含んでいる。それは、研究者としての存在を証すものである。それが、複数の研究者と共有するタイトルと同一であるはずがない。私は、この5部構成が成功していないことが、鳥越スクールの特長を表していると思う。そして、ここにも研究に囚われた人間の生に対する鳥越さんの肯定を見てしまうのである。
注
1) 本稿で言及した本書所収の論考は次のとおり。本文中では「[著者の姓]論文」と表記した。
- 足立重和「生活環境主義再考―言い分論を手がかりに」(序章)
- 土屋雄一郎「誰が「負財」を引き受けるのか―震災がれきの広域処理に向き合う地域社会の応答」
- 閻美芳「ムラ入り賦課金をめぐる「共在性」の論理──茨城県石岡市X地区におけるよそ者の分離/包摂の事例から」
- 金菱清「オーダーメイドの復興まちづくり─東日本大震災の被災沿岸における大規模集団移転の事例から」
- 金子祥之「放射能汚染が生む交換不可能性と帰村コミュニティ―福島県川内村における自然利用と生活互助のいま」
- 山室敦嗣「原子力施設をめぐる周囲コミュニティの形成─JCO臨界事故を経験した住民のスペクトラム的思考」
- 五十川飛暁「アンダーユースな資源の差配にみるコミュニティの空間管理─茨城県X集落における河川敷利用の事例から」
- 鳥越皓之/足立重和・金菱清(聞き手)「生活環境主義とコミュニティのゆくえ」(補論)
2) 私が生活環境主義の陳腐化を指摘したことは間違いないが、その点をクローズアップされるのは本意ではない。レビュー論文を書いた動機はその点よりもむしろ、それまでの生活環境主義批判のほとんどが的外れで、おおいに不満を感じていたからであった。
3) 直感を述べるにとどめるが、こうした議論は吉本隆明の転向論とも響き合うように思われる。
文献
荒川康・五十川飛暁, 2008, 「環境社会学における生活環境主義の位置―「経験論」を手がかりとして」『兵庫県立大学環境人間学部研究報告』10, 77-88.
松村正治 2007 「『生活環境主義』以降の環境社会学のために」舩橋晴俊・平岡義和・平林祐子・藤川賢編『日本及びアジア・太平洋地域における環境問題と環境問題の理論と調査史の総合的研究』(2003-2006年度科学研究費補助金研究成果報告書、研究代表=帆足養右、課題番号1533011): 273-288.
森有正 1970 『生きることと考えること』講談社.
謝辞
本稿を書く前に、本書をめぐる雑談に応じてくださった箕浦一哉さん(山梨県立大学)、平井太郎さん(弘前大学)に感謝を申しあげる。