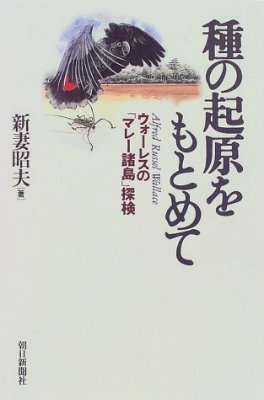昨秋、同僚であった新妻さんが亡くなりました。
その時から5か月近く経ちますが、新しい年度に変わる前に何か書いておきたいと思って、今回は毎日出版文化賞を受賞したこの本を取り上げることにしました。
新妻さんを形容するのに適当な言葉は、おそらく、自由でしょう。
同僚でジャーナリストの武田徹さんも、ご自身のサイトに新妻さんを偲んで自由について書いています。
(→「われらフリーター同志」)
まずは、普段の格好が自由で洒落ていました。
長く伸ばした髪を後ろで束ね、いつもジーンズを履き、手術した喉をいたわるためにスカーフを巻き、ときどき声が出にくくなるのでペットボトルに水を入れて持ち歩く、これが新妻さんのスタイルでした。
さすがに、入学式や卒業式ではスーツを着ることもありましたが、それ以外は、公式な式典でも、たいていジーンズで通していました。
私はただ面倒なだけでジーンズを愛用していますが、新妻さんが近くにいなかったら、服装のTPOについて頭を悩ませていたかもしれません。
もちろん、新妻さんの魅力はそうした外見ではなく中身にありました。
それは、学ぶことに自由で貪欲であったことです。
私が今の大学で職を得たときには、すでに新妻さんは数多くの著述や翻訳の仕事をされており、サイエンス・ライターとして著名な方でした。
しかし、そうした社会的な評価をまったく鼻にかけることはなく、常に疑問を持ち、それに少しずつでも答えていこう姿勢が感じられました。
食堂で会うたびに、あるいは研究室を訪ねるたびに、新妻さんはご自身が今何を考えているかをお話になり、それに対するコメントを私に求めました。
よく2人の間で話題になったのは、花についてでした。
新妻さんの研究業績では、学生時代のアザラシの動物行動学研究と今回取り上げたような博物学史研究が有名でしょうが、最近は園芸(特に花)の研究を進めていました。これは、聖書・国際・園芸の3本柱を教育の中心に位置づける大学で、独自の角度から園芸にアプローチしようという試みだったと思います。つまり、大学の存在価値、特に園芸教育の意義付けを、実証的な研究によって再考しようとしていたと私は理解しています。
新妻さんは、イギリスで園芸が普及していった当時の古い園芸雑誌を調べていました。
また、大学の創設者・河井道によって、海外から園芸教育が導入された経緯を調べていました。
こうして原点に立ち返ることで、今日では見えにくくなっている何かを園芸から救い出そうとしていたようです。
新妻さんは、「イングリッシュ・ガーデンは里山と同じなんだよ」とおっしゃっていました。
イギリスで園芸が定着していく頃の標準的な庭を見ると、そこに植えられる植物は合理的にデザインされていると言います。
手入れのしやすさを考慮して、その地域の自然に合った種が選ばれており、手前から奥にいくにつれて粗放的な管理でよいものを配置するようです。
イングリッシュ・ガーデンと聞くと気取ったイメージがあるかもしれません。
私も、そうした通俗的なイメージしか持ち合わせていなかったのですが、そこには自然への働きかけを通して培われた合理性があると教えられたのです。
まさに、これはNORAなどが理想化して語るときの里山モデルとそっくりです。
新妻さんは、そこから野生種と園芸種の境界に切り込みます。
自然保護運動、里山保全活動に関わっている人の中には、野生種と園芸種を峻別して、前者を大切に思うものの、後者にはほとんど価値を認めないというタイプが多いです。
しかし、新妻さんは、園芸の原点を探りながら、こうした区別を相対化しようと試みます。その流れで、半栽培という概念にも注目されていました。
こうした思索を通して、環境時代の今、エコロジストから冷遇されやすい園芸種の価値を野生種とあわせて見出そうとしていたように思います。
新妻さんは町田市の花壇コンクールの審査委員を務めていました。
このコンクールは、エコロジストには評判が悪いものです。見方によっては、ただ町田市で育てている花の苗を植えて、花壇を美しくすることを競うことにどういう意味があるのかと批判的な立場をとる方もいます。
町田市民である私も、この花壇コンクールに対して冷淡でした。
つまり、ここから何も学ぼうとしていなかったのです。
新妻さんは私にこのコンクールの経緯を説明してくださいました。
町田市が昭和40年代に団地建設ラッシュを迎え、コンクリートの町と化してしまう危機感から始まったのが原点でした。
このコンクールに直接的な影響を与えたのは、宇部市の花いっぱい運動でした。
セメント産業で有名な宇部市は、高度経済成長期に粉塵公害で白く埃っぽくなってしまいました。そこで、まちを花とみどりで豊かなまちにしようと市民が協力して始めたのが、花いっぱい運動だったようです。
さらに、このルーツを探っていくと、1952年に松本市の小学教員が始めた運動に行き着きます。
それは、戦後、まちが荒廃して人びとの心も余裕を持てない中で、花を通して心を豊かにしようという試みでした。
こうした話を伺い、2人で話し合っていくにつれて、新妻さんが追っているテーマが、非常に魅力であることに気づくようになりました。
それで、最近、私も沖縄の緑化・修景を調べるようになったのです。このテーマは、新妻さんから受け継いだものと思っています。
新妻さんは花壇コンクールの欠点に目をつぶっていたわけではありません。
始めた当初の目的を理解しながらも、それが次第に時代とそぐわなくなっていることも指摘されていました。
このコンクールが、徐々に地域の生態系にも配慮する方向へと移行できないかを考えていました。
しかし、頭ごなしに変更を命じるのではなく、関わっている行政職員や市民ボランティアが納得しながら、環境時代に即して変化していく方策を検討されていたようです。
そして、こうした実践に関わりながら、野生種/園芸種という括り方を捉え直し、もっとすっきりと把握できる考え方を模索していたようです。
それは、きわめて科学的な態度だったと思います。
新妻さんは、「学生には花を持ち歩いて欲しい」とか「花の似合う女性になって欲しい」と、おっしゃっていました。
新妻さんの女性に関する発言はときどきセクハラ的で、それもまた新妻さんらしかったのですが、この言葉は私も素直に受け取れました。
多くの学生たちが自由に花を手にして歩いていたら、そのキャンパスは何とも素敵だろうと想像してしまいます。
このようなことをさらりと言えるのは、学生が素敵な大人になって欲しいと強く願っているからなのでしょう。
そうした学生に対する愛情の深さを、しばしば感じることができました。
うまく、まとめられません。
新妻さんに関するエピソードは、さらに2-3用意してあったのですが、
ますます話が混乱しそうなのでやめておきます。
最後に本の内容にふれましょう。
『種の起原をもとめて』(ちくま学芸文庫、2001年)は、ダーウィンとほぼ同時に、独自の調査研究で進化論を着想したウォーレスについて書かれた本です。
この本は、文献を渉猟しただけではなく、実際にウォーレスが探検したマレー諸島やイギリスの居住地なども訪ね歩き、そこで見聞きし、感じたことを踏まえて書かれているところが特徴的です(これを「ウォーレスごっこ」と呼んでいます)。
また、ときおり挟まれる新妻さんからウォーレスへのコメントが温かいです。
新妻さんは『ダーウィンのミミズの研究』(福音館書店、2000年)というダーウィン関係の本も著しています。子ども向けに書かれたものですが、私の好きな本です。
内容は、ダーウィンが40年以上もかけて取り組んだミミズの研究の概要が紹介されています。
しかし、それだけではなく、ここでは「ダーウィンごっこ」の話があります。
イギリスまで足を運び、ダーウィンが実験した場所で土を掘り返して、ミミズが1年間に土をつくる厚さを推測したことが書かれています。
フィールドワーカーらしく、常に現場を重視しながら、科学的に証拠を集め、論理的に考える姿勢を大切にされていました。
この子ども向けの本からは、そうした科学への愛が伝わってきます。
もう1つ、里山に関するところで、新妻さんも翻訳者の1人であるデビッド・タカーチ『生物多様性という名の革命』(日経BP社、2006年)を挙げておくべきでしょう。
里山は生物多様性が高いということから、および1990年代以降、社会的に評価されるようになりましたが、その生物多様性という概念がどのように生まれ拡がっていったのかを、著名な生物学者へのインタビューをもとに考察したものです。
生物多様性について、まじめに考えようとする場合に、避けて通れない本の1つだと思います。
その他、亡くなる前にまとめられた『進化論の時代―ウォーレス=ダーウィン往復書簡』(みすず書房、2010年)や、ウォーレスの『マレー諸島』』『熱帯の自然』など、いくつも重要な文献を翻訳されていますし、著書も数多いです。
これを機会に、どれか1冊でも新妻さんの作品に触れていただければ嬉しいです。
私は、新妻さんが花に着目して進めていた研究を読みなおして、遺志を少しでも引き継ぎたいと思っています。