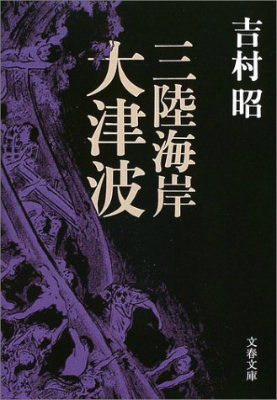中高時代、吉村昭氏の文庫本は家の書棚にいくつも置かれていました。
読書好きの弟がそれを読んでいたのですが、当時の私はその硬質な文体を敬遠していました。
しかし、近頃は何かとかこつけて読んでいます。
当時の本は処分してしまいましたが、今では吉村昭の本がかなり電子書籍化されているので、読もうと思ったときにすぐに読み始められます。
最近は、かつて苦手だったその文体が、とてもしっくりくるから不思議です。
今回のコラムでは、その何かとかこつけて読んだ3冊を取り上げます。
吉村昭『三陸海岸大津波』
本書は1970年に書かれたものなので、刊行後40年以上の歳月が流れています。
2011年3月11日以降、急に売れて本屋でも平積みとなり、あらためて多くの読者を得ました。
私もそうした読者の1人でした。
本書は、明治から昭和にかけて三陸を襲った3回の津波について記しています。
すなわち、2万人を超える死者を出した明治三陸地震の津波(明治二十九年の津波)。
死者・行方不明者が3千人以上に及び、特に岩手県・田老で甚大な被害が生じ、その後の巨大防潮堤建設へと繋がる契機を与えた昭和三陸地震(昭和八年の津波)。
さらに、地球の真裏近くで発生したために津波が収斂しやすく、「のっこ、のっことやって来」て大きな被害を出したチリ地震津波です。
東北三陸地方は津波の常襲地です。
著者は、この地方を繰り返し襲った津波の被害について、そして、沿岸に住む人びとがどう向き合ってきたのかを記述しています。
本書を読むと、津波の怖さは後世に伝えてられてきたと同時に、時が経つと薄らいでいくという身も蓋もないことを教えられます。
ここに書かれていることは、地震大国に住む私たちにとって、共有すべき大きな遺産と言えます。
こうした歴史から何を学ぶのでしょうか。
津波の体験を忘れないようにと言うのはたやすいですが、忘れていくことを前提にするべきだと思います。
被害の記憶が薄れた頃に津波に襲われたとしても、それでも安全なまちをどうつくるのか、と考える必要があるでしょう。
自然災害に対する人間の力があまりにも弱かった頃は、津波襲来による被害を天災として諦め、受け入れられたかもしれません。
しかし、現代の私たちには自然災害に備えられる力を持つに至りました。
土地を嵩上げしたり、巨大な防潮堤を建設したり、それも、固定式ではなく可動式を検討したりと、津波被害を最小限に抑えるために対策を練っています。
もちろん、かかる費用も検討しなくてはいけませんし、そもそも、対策後にも住み続けたくなる環境なのかという問題もあります。
科学技術が進んだために、かえって、社会には数多くの選択肢を与えられ、どれを選んでも十分には満足が得られないという状況に置かれています。
三陸地方に限らず、地震津波は日本列島を繰り返し襲ってきました。
それは、1,000年に1度の大津波であっても、地質年代のスケールで考えれば、周期的な現象です。
地球の視点からすれば当たり前に生じること津波に対して、私たちはどう対策を講じるべきか深く悩まざるをえません。
それだけ、人間は小さな存在だと捉えることもできるでしょう。
しかしだからこそ、津波対策、さらに一般化して防災とは、私たちの社会が力を合わせて考える価値があるとも言えます。

吉村昭『熊嵐』
著者は、この津波被害のように、厳しい自然と向き合ったときの人間の弱さや小ささを、(その中にある逞しさや強かさなども)しばしば題材に取り上げます。
特に『熊嵐』は、そうしたテーマ性がはっきりと見られる作品です。
本書を読んだきっかけは、かつて私のゼミに所属していたOGが読んでいたことを、最近になって思い出したので、彼女のことが気になって読んだ本です。
このOGの学年は、2011年3月に卒業したのですが、震災の影響で卒業式が中止となり、学生としての区切りを付けられないまま社会人となりました。
今年の夏、同期の別のOGが研究室を訪ねてくれたことが契機となり、久しぶりに集まろうという話になりました。
さらに、どうせ集まるならキャンパスに集い、式で着るはずだったガウンを着用して写真撮影するという企画となりました。
(12/7(土)、約20名の卒業生が集まり、ガウンを身につけて写真撮影しました)
この企画が決まった頃、誰が集まるかと予想しながら、卒業式を挙げられなかった同期のことを1人ひとり頭に浮かべているうちに、読書好きだった彼女が卒論のテーマを決める際に、本書を読んでいたことを思い出しました。
彼女は、同期のメンバーとも連絡が取れなくなっていて、今度の企画についても伝えられなくなっていました。
それでこの本を読んで追体験したくなったように思います。
話は日本史上最悪の獣害と言われるヒグマによる人的被害を扱っています。
三毛別羆事件と言われ、北海道の三毛別という開拓村が舞台です。
この本を読むと、人を食って味をしめたヒグマに対し、夜には真っ暗となる中では、鉄砲を持たない人間が何もできないことを痛感させられます。
さらに、この弱い人間がおおぜい集まっても、ほとんど何も役に立たないどころか、むしろ、ばらばらで混乱を招くことが示されています。
ただ、本書は、獰猛なヒグマの前で人は圧倒的に弱いという自然(野生動物)-人間のシビアな関係を示すだけの本ではありません。
それが、絶えず緊張感を生んでいることは間違いありませんが、自分がヒグマに襲われるかもしれないという環境で、人びとがどう考え、どう行動するのかが、たくみに描かれています。
恐怖の中で、どのような集団心理が生じるのか、最終的な目標である熊を仕留めることのために、リーダーは何を優先して考え、どう判断し、行動したのか。
史実に基づいていますが、ノンフィクション的な小説で、ぐいぐい引き込まれます。
なお、この凄惨な獣害事件の現場は、現在、三毛別羆事件復元現地として、事件の解説板、犠牲者の慰霊碑、さらにヒグマの像があるそうなので、一度立ち寄ってみたいと思っています。

吉村昭『陸奥爆沈』
最後に取り上げる『陸奥爆沈』は、今年の夏に反原発の島として有名な祝島を訪れたことがきっかけで読みました。
祝島へ行きたいというOGに誘われて、一緒にフィールドトリップに出かけたのですが、祝島に行くついでに立ち寄れる場所がないかと探していると、周防大島にある陸奥記念館のことが気になったので訪ねることにし、行く前に本書を読んでみました。
(祝島に行く際には、山秋真『原発をつくらせない人びと―祝島から未来へ』(岩波新書、2012年)を読んでおくことをお勧めします。)
陸奥は、長門とともに連合艦隊の旗艦として長く活躍し、大和や武蔵が建造されるまでは最強の戦艦だったようです。
それが、1943年に周坊大島沖合で原因不明の爆発を起こし、1,000人余りの将兵とともに瀬戸内海に沈みました。
1970年になって、ようやく艦体の一部が回収され、日本各地で陸奥の装備が展示されました。
陸奥記念館は、この陸奥爆沈の現場に近い場所に建てられています。
館内には、亡くなった方の遺品や遺族の方々から寄せられた資料、引き揚げ作業の様子、復元された船室などが展示されています。
また、併設する公園には、引き揚げられた船体の一部や、鎮魂碑が建立されています。
著者は太平洋戦争に関する作品を相当書かれていますが、この本はその中にあって、一風違ったものとなっています。
それは、本書が著者による陸奥爆沈の原因探しの旅を中心にしてストーリーが描かれているからです。
著者は、ある特定の人物に視点から見える世界を冷静に描写することで、作品にリアリティをもたらすことが抜群にうまいのですが、本書では、著者が推理小説のように理詰めで爆発の原因を探っていくというかたちをとっています。
米軍の魚雷による爆発、スパイによる破壊工作、自然発火による暴発など、考えられるいくつかの選択肢を一つひとつ消去していき、可能性が高い原因を探り当てることになります。
そこに至る推論を読み進めていくと、軍隊という社会集団が抱える病理に突き当たることになります。
本書によると、陸奥は当時世界最強の武器を装備した戦艦でしたが、あっけなく沈没したのは、余りも人間的な理由でした。
この事実を重く受け止めれば、いかに強力で安全な機械を作りだしたとしても、それは人間が作る限り、やはり人間的な理由で、簡単に壊れてしまうものだと考えるべきなのでしょう。
それは、今後、原子力発電所とどう向き合うかという社会的課題を考える際にも、前提とする必要があるだろうと思います。
NPOにはビジョンが必要ですが、将来のあるべき社会を構想する際に、過去を参照することは必須だと考えています。
吉村昭氏が残された数多くの記録文学・歴史文学の作品は、さまよう私たちに指針を示してくれると思います。