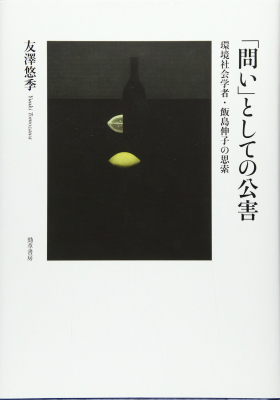1月下旬~2月中旬にかけて、三島、川崎、西淀川を立て続けて訪ねた。
これらは、日本の公害史、特に大気汚染問題の歴史をたどるとき、たいてい参照される有名な地域という共通点がある。
当初は、公害史を振り返るという目的が明確ではなく、気になるイベントをチェックし、参加できるものを挙げていったら、こうした地域が並んだということだ。
行きたい場所を探しているうちに、問題意識が覚醒されたのだった。
1/27(火)は、三島市主催の市民向け講座「石油コンビナート反対運動から50年」に参加した。
これは、三島市民が石油コンビナートの進出を阻止して50年が経過したことから、キーパーソンと研究者から、当時の様子やこの運動の意義を聞くというものだった。
石油コンビナートの進出計画に対して、不安を覚えた市民たちが、四日市の公害の実態を見学に行くなどして勉強を重ね、最終的に行政が進出を拒んだという有名な話だが、直接、当事者の声を聞くのは初めてだったので刺激的だった。
2/8(土)は、NPO法人川崎フューチャー・ネットワーク主催の「今、川崎の公害を振り返る―50年前の川崎から君へ」に参加した。
これは、高度成長期に大気汚染を経験した川崎において、行政と市民のサイドでそれぞれどう公害対策に向けて取り組んできたのかという話だった。
そこには、公害は解決したように言われているが、本当にそうなのかという問いが含まれていた。
2/11(水祝)は、あおぞら財団(公益財団法人公害地域再生センター)主催の地域の”おもろいわ”を掘り起こす「おもろいわ西淀川 大集合!」に参加した。
これは、西淀川大気汚染公害の経験を無かったことにするのではなく、それも受けとめて誇りを持って暮らすために西淀川の良さや面白さを共有するプロジェクト「おもろいわ西淀川」の成果を確認し、これからをどう作っていくかを考えるというイベントであった。
当日のゲスト(一社)あがのがわ環境学舎の山崎陽さんから、新潟水俣病を経験した阿賀野川流域で地域の方と一緒に本音を語り合う寄り合い「ロバダン!」を積み重ねてこられた経験も聞くことができた(今年は、新潟水俣病公式確認から、ちょうど50年に当たる)。
こうした3か所の取り組みは、高度成長期に経験した過酷な公害を、解決したとして過去のものとして済ませたり、無かったこととして忘却したりするのではなく、そうした時の流れに抗いつつ、当時から50年が経過した今日、その経験を各地域のこれからに生かそうとするものであった。
こうした問題意識は、私も共有している。
先行きが不透明な今日において、未来を構想しようとするときに、過去をよく見つめることが大事であろう。
公害の経験から、時代の制約を超えて学べることはあるはずである。
そもそも、患者さんはいらっしゃるし、係争中の裁判も続いている。
公害は終わったわけではない。
そこで、本書である。
著者も、いや、著者こそ、すでに終わったとされがちな公害について、あらためて深く考察する。
「公害の時代は終わり、今は地球環境問題の時代である」とか、もっと短縮化して「公害から環境へ」というように、公害と環境(問題)を発展段階として捉えることを拒絶する。
また、公害を大気汚染、水質汚濁、騒音、振動などといった項目の科学的数値が健康に被害を与えるほどに大きいことだという公害像を壊す必要があると述べる。
そして、そもそも公害とは、最優先される経済活動に連動して暮らしが激変し、その中で生じた「これは一体どういうことか」という「問い」があったことを確認する。
被害者は、工学的に捉えられる汚染の程度や、医学的に捉えられる健康被害の重さなどだけでは収まらない、社会的な矛盾、格差、差別、不均衡に向けても「問い」を発していた。
公害とは「問い」である。
著者はこう言い切ることから、閉じこめられつつある公害像をこじ開け、現代に生きる私たちにとってもアクチュアルな視野が見いだせないかと述べるのである。
ところで、著者は1980年生まれと若い。
だから、公害の歴史を自らの体験をもとに振り返るようなことはできない。
そこで、本書は副題に「環境社会学者・飯島伸子の思索」とあるように、1960年代半ばから約35年にわたって公害・環境問題に取り組んだ1人の女性研究者・飯島伸子(1938-2001)のあゆみを手がかりにして、考えを進めていく。
飯島が公害問題に取り組み始めた頃、周囲は工学者や医学者ばかりで、社会科学でも経済学的な研究はあったが、社会学的なアプローチはほとんど無かった。
しかし、飯島は、スモン患者をはじめ多くの被害者の声をじっと聞く中から、従来の工学や医学あるいは経済学の学問手法では捉えられない不可視の被害を凝視し、丁寧に書き留める。
筆者によれば、「その(飯島の)筆致は、他者から認識されないと思われることがらにさしかかるほど、速度を落とし、より丁寧に語ろうとする傾向をもつ。」
たとえば、公害による身体的な障害が重い場合、それは第三者からも見えるので、たとえば直接的な医療費は補償されやすい。
しかし、中軽症の場合、周囲から見えにくいために、症状を緩和するために通う鍼灸やマッサージの費用、通院に必要なタクシー代など、生活上必要な間接的な費用は請求できない。さらに、訴訟を選ぶ人々は、しばしば「カネとり」と差別される。
こうした見えにくい被害は、近しい家族や親族などからも理解されずに、関係が悪化したり、断絶したりすることもある。
被害とは何だろうか。
被害者個人の身体的な症状の軽重で判断できると考えれば、そこに社会学が入り込む余地はない。
しかし、著者は飯島が徹底して被害者の苦悩を掘り起こし、被害の存在を明らかにしようとしたアプローチについて、「人間の精神あるいは尊厳を根源的なところで成り立たせているのが他者との関係なのであり、これが崩壊していくことこそが「被害」と呼ばれるべきではないか、との提起でもある」と説明している。
こうした見方は、まさに社会学的であり、飯島が個別具体的な「被害」に向き合うなかで獲得した方法論と言えるだろう。
そして、こうした視点は、たとえば、福島第一原子力発電所事故にともなう放射線被曝について考えるときに、大いに生かせるはずである。
つまり、被曝量が少なければ被害が少ない、あるいは無いというわけではないのだ。
被曝のリスクによって、そのリスクをどう見積もるかによって、家族・親族、地域社会など、人と人の間にひび、亀裂が入っていくことがある。
それは、健康被害と比べて軽く見られているかもしれないが、人が生きていく上で最も重要な人間関係を損なわせている。
こうした「被害」について、被害者に寄りそいつつ、耳を傾ける必要がある。
「問い」としての公害は、このように今でも十分に生かせるのである。
本書では、飯島による一連の公害・環境問題の研究業績にあって、異色の感がある美容の社会学にも注目する。
飯島は、美容師が多量の化学物質に曝される職場環境にあることや顧客が化学物質を用いた美容施術により被害を受けるケースがあることに注目した。
これは、一般的な公害・環境問題という枠には入りきらないものの、飯島にとっては、労働環境問題(労働災害)、消費者環境問題(消費者災害)であり、独自の環境問題の解釈には含まれていた。
しかし、環境問題を地域という範囲で考える場合、こうした飯島の解釈は奇異に映る。実際、環境問題に対して社会学的にアプローチする場合、現地でのフィールドワークに基づき、データを収集して議論することが多く、特に環境社会学では、そうした手法を得意としてきた。
飯島の「美容の社会学」は、全国にある美容院で発生しうる労働者(美容師)と消費者(顧客)の「環境」問題を扱ったので、環境社会学の業績としては、ほとんど無視されてきた。
西淀川にしても川崎にしても、50年前に比べると大気はきれいになった。
その背景には、公害対策が進んだこともあるだろうが、鉱工業の第二次産業から商業・サービス業の第三次産業へと産業構造がシフトして、住宅地と工場が混在する地域が減少したことも影響しているだろう。
すると、生産の現場に近いところで公害が発生するというパターンよりも、たとえば、全国に流通されている美容品で肌のトラブルを抱えるというように、消費の現場で問題が発生していることの方が現代的な問題なのかもしれない。
だから、地域を超えた「環境」問題について取り組んでいた飯島は、むしろ普遍的な視点を持っていたとも言える。
飯島は、被害者へ聞き取り調査を重ねながら、まだ名前の与えられていない被害の存在を探り当てようとした。
そうした被害は、原因追及が難しく、また個人的な問題(体質等)とされやすいので、当事者は孤立しがちで、支援者もなく、なんとかやりくりして暮らしているかもしれない。
飯島の視点は、こうした現在でもどこかで生じているであろうこうした被害に目を向けさせてくれる。
本書では、著者の適切な導きによって、このことに気づかせてくるのである。
本書冒頭の問題意識の立ち返ると、著者が飯島とともに抗うのは、環境問題を主として人と環境の関係の問題として扱うことである。
そうすると、人と人の関係に焦点が当てられなくなり、人と人の間の格差や差別、権力関係などが軽視されやすくなる。
しかし、被害をじっと見つめ、被害者の声に耳をすませていくと、他者との関係こそが人に喜びを与えてくれるものであり、それが損なわれることこそが被害ではないのかという「問い」にいたる。
こうした人と人の関係は代替不可能で、金銭では補償できない。
飯島の、そして著者の「問い」に対して、私たちは応える術を持っているのだろうか。
著者の友澤さんが、飯島の研究をしていることを知ったのは10年ほど前であった。
ある研究会で、友澤さんは本書に収められている議論の一端を披露されたのだが、そのときの衝撃は忘れられない。
私は飯島による環境社会学の入門書や、飯島が編集したテキストを読んで、この学問に入ったし、また、生前の飯島に1回だけお目にかかったことがある。
だから(というのは言い訳に過ぎないが)、飯島を研究対象にするというアイデアは考えもつかなかった。
飯島がこの世を去ったことにより、彼女が書いたもの、集めた資料、残したノートなどをまとめてアーカイブズとして保存しようというプロジェクトが進められた。友澤さんもそれに参加することができたことや、追悼集が編まれて、これまで飯島に近しい者しか知り得なかったことまで、一般にもアクセスしやすいかたちでまとまったことにより、飯島を研究しやすい環境が整いつつあったという面はあるだろう。
しかし、それを差し引いても、まずは着眼点の鋭さに驚いたのであった。
さらに、発表に際して用いる言葉遣いが魅力的でセンスを感じたのだった。本書でも、私はこのように表現できたらいいのにと感じたところが何箇所もあった。
適切に正確に言葉を連ねていくところと、ときどきドキッとする言葉を使うところとの強弱、濃淡の付け方が上手で、書き手として優れているから、文章を読むのが楽しいのである。
私は飯島の書いたものは普通に刊行されているものしか読んでいないけれど、おそらく、著者は飯島よりも、飯島自身が抱えていた「問い」を、本書で明瞭に表現したように思われる。
飯島は優れた研究者によって、時を超えた普遍性を持っていることが示された。
それは、著者の功績であるけれども、飯島の研究がそうした高いポテンシャルを持っていたからこそ、優れた研究者を招き寄せたという面もあるだろう。
飯島の研究の原点は、著者に影響を与え、その著者はあたかも飯島に取り憑かれかのように、私たちに対して「問い」を投げかけている。
本書は、刊行後、全国紙に書評が掲載され、2014年度の藤田賞(公益財団法人後藤・安田記念東京都市研究所)を受賞したように、間違いなく良書である。(飯島も1978年度に藤田賞特別賞を『公害・労災・職業病年表』で受賞している。)
公害は終わった。環境は説教臭い。
こんなふうに思っている方や、こうした言い方にもやもやを感じる方に、ぜひ一読を勧めたい。