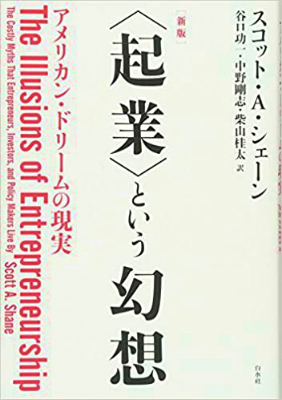2020年3月末をもって、15年間勤めた大学を退職した。
3年前、任期のない教員から任期付きの特任教員へと契約を変更したとき以来、このことは既定路線として過ごしてきたけれど、いざ、部屋に置いていた私物をすべて運び出し、鍵を大学に返して部屋を明け渡したときは、一抹の寂しさを感じた。
一方で、この1~2ヶ月間は、この引っ越し作業のことが気がかりで仕方なかったので、一段落付いて肩の荷が下りたようにも感じた。室内の私物のうち、必要な本や資料を自宅に移し、同僚や友人、大学などで引き取ってくれるものは譲り、残った不要なものは可能な限り分別した上で廃棄した。整理してみると、要らないものが多かったことから、これまで大量のごみを抱えて過ごしていたことに気づかされた。
facebookやこのコラムなどを通して大学教員を辞めると伝えると、多くの方々から温かいお言葉をいただいた。その中には、大学を辞めて起業するというイメージを持たれている方もいらっしゃる。
たしかに、4月以降は自分で仕事を得てお金を稼がないといけないので、仕事づくりをしていく必要があるのは間違いない。しかし、現時点では明確な事業計画が立っていないので、むやみに仕事を引き受けるよりも、もう少し自分で考えたり、人と話したりする時間を取ろうと考えている。
また、私はあまり起業すること、それ自体に関心があるわけでもない。目的や目標に応じて、自分を生かせると思えるならば、雇用されること、人の下で働いてもいいと思っている。
さて、今回取り上げる本書は、タイトル通りの内容である。本書の帯には、「会社を辞めて「起業」に走る前に・・・」という警句が書かれているが、そういう本である。
全編を通して、起業に関する一般的なイメージを覆すために、具体的な事実を示して反証するという形式がとられている。そういう意味では、昨年、国内でベストセラーとなったハンス・ロスリングほか『ファクトフルネス』(2019年、日経BP)のような印象を受けた。
タイトルとイントロダクションを読めば、著者の言いたいことはほぼわかってしまうので、議論の展開はスリリングとは言えないが、具体的に示される数字には興味深いデータが少なくない。
著者は、典型的な起業家のイメージを、次のように描く。
すなわち、起業家とは、「数人の仲のいい友人と数百万ドルのベンチャー資本を調達して会社をおこし、特許によって守られた新発明の装置を開発するような、ジェット機にしょっちゅう乗るシリコンバレー在住のエンジニア」で、「数千人を雇い、四年後には株式を公開し、その創業者と投資家のために百万の富を生みだすことになる」というものだ。
しかし、現実はこうした神話とは似ても似つかぬもので、ずっとありふれた職業である。たとえば、
・アメリカ全世帯の11.1%は自営業。
・2005年には、18歳~74歳の約13%が新しいビジネスを始めようとしていた。
・全人口の40%が、人生の中で一度は自営業に就く。
イントロダクションには、本書を読み通してもらうために、起業に関するいくつかの事実が挙げられている。
・アメリカは、以前に比べるなら起業家的ではなくなっている。
・アメリカは格別に起業家的な国とは言えず、ペルーの方が3.5倍も起業する人がいる。
・起業家は、建設業や小売業などのありふれたローテク産業で事業を始めることが多い。
・転職の多い人、失業している人、稼ぎの少ない人が、起業する傾向がある。
・典型的なスタートアップ企業の資本は25,000ドルで、多くは本人の貯蓄である。
・典型的なスタートアップ企業は、成長プランも持たず、誰も雇用しない。
・典型的な起業家は、雇用されるよりも長時間労働し、低い額しか稼いでいない。
そして、本書の結論は、「無知な起業家には、ぶざまな決定しかできない」「起業家になろうと考える人は、新たなビジネスの成功に必要なファクターを知っている必要がある」とまとめられる。
たとえば、資本金が豊富で、株式会社として組織され、明確なビジネスプランを持つ起業家たちのチームがフルタイム・ベースで創業し、他人が見逃している顧客に製品を売ろうとしている比較的大きなビジネスは、そうでないビジネスよりも成功するだろうと認識する必要があると言うのだ。
こうした経営的な観点からすると、起業の現実は理想からかけ離れたものであるから、公共政策によって単純に起業家の数を増やそうとすることに筆者は反対する。費用対効果を考えて、効果的にスタートアップ企業を支援すべきと言うのである。
なるほど、こうした著者の結論は、起業に対する神話を打ち砕き、起業しようと興奮気味に考えている人に冷や水をあびせるには十分である。そのために示されるデータは、どれも説得力がある。
また、米国の経営学的な実証研究の厚みも感じられる。起業熱にうなされて、有り金を失うよりは、冷静に計画を立てて、長期的な視野に立って事業を起こす方がいいのは確かであり、そういう点で、本書は愛のある提言にあふれている。
しかし、結論自体に、さして面白みは感じられない。
私は本書が脇に置いているストーリーに興味を抱いた。
たとえば、起業の半数が在宅ビジネスであること、起業する動機の多くは他人の下で働きたくないという理由からであり、平均的に見て、男性に比べて女性が創業したビジネスの業績が低いのは、一般に女性は金融面での高い目標を上げるのではなく、育児など生活の時間を柔軟に確保したいために起業するから、など。
こうした起業家たちは、仕事だけではなく生活も含めて、ワーク・ライフ・バランスを取ろうとしているに違いない。
私の感覚では、そうした起業は全然悪くないし、低成長時代においては、むしろ健全でさえあると思う。
たしかに、いくら儲けるのかという尺度から起業の現実を見れば、著者にとって歯がゆいばかりであろう。しかし、読者として期待されている起業家やその予備軍にとっては、そうした愚かな選択もまた人生であり、言われることはもっともだけれど、余計なおせっかいだと、知ったことではないと言いたくなる人もいるだろう。
私も、そう言いたくなるタイプの一人である。
本書を訳した3人もまた、私のような感覚を共有していると思われる。
アメリカ社会を起業に注目する場合、「アメリカン・ドリーム」を体現した一部の例外的な人ではなく、アメリカの地の塩たる「自営業者(self-employed)」の方に目を向けることもできる。むしろ、その方が現実をよく見ることになるし、トクヴィルが『アメリカのデモクラシー』で描いたような、小さい事柄を自主的に処理する能力が陶冶される社会背景を理解することもできる。
訳者のあとがきには、「独裁者が恐れるのは、自分の足でしっかと立つ独立自営業者である」という言葉が紹介されている。これは訳者が、トクヴィルの言葉だと信じ込んでいた言葉であるが、私はこの言葉に共感する。自営に価値を置くならば、それは、個人的な利益のためではなく、自分のアイデンティティのため、さらに、そうした個々の自由が保証されるような社会のためだと思っている。
最後に、私がNORAの運営を考えるときに参考にしている大阪のNPO法人里山倶楽部の活動理念の変化にふれて終えたい。
先日、事務局を務めている寺川裕子さんに会った。里山倶楽部では、1995年の団体設立以降、「好きなことして、そこそこ儲けて、いい里山をつくる」という魅力的な活動理念を掲げていたが、2016年からは「新しい“里山的”生き方・暮らし方の提案」に変更した。
その理由を伺ったところ、「そこそこ儲け」るという言葉に惹かれて、お金が稼げるからと近づいてくる人が多いのに対して、現実はほとんど儲からないという現実を踏まえて、仕事だけではなく、暮らしも含めた理念に変えたということだった。
経営的な観点からすると、厳しい現実を受け入れた消極的な変更に見えるかもしれないが、私はそのように思わなかった。むしろ、里山倶楽部が大事にしていることの核を取り出したら、稼ぐことよりも生き方・暮らし方に関心があって、起業したことに気づかれたのだろう。それで、その原点をシンプルに伝えることにしたのだと思う。
今後、私がどのようなかたちで仕事を進めていくのか不透明であるが、私もまた、小さい事柄を自分で納得できるように処理できる領域を保ち、そこを自主的に処理する能力を鍛えたい。
そのための手段が、起業であるかどうかは、もう少し時間をかけて考える。