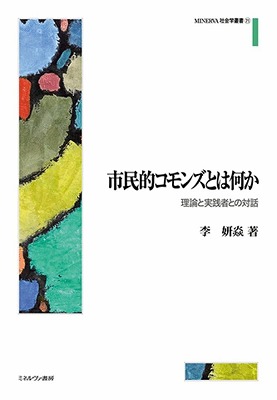李妍焱『市民的コモンズとは何か―理論と実践者との対話』(2025年、ミネルヴァ書房)
著者の李妍焱(リ・ヤンヤン)さんは、駒澤大学で教える社会学者で、専門は日本と中国の市民社会とソーシャルイノベーション。
また、日中市民社会ネットワークの代表として、東アジアにおいて市民社会の架け橋となる活動も精力的に進められてきた。
私がヤンヤンさんのことを知ったのは、『中国の市民社会―動き出す草の根NGO』(2012年、岩波新書)を出版された頃だった。
その頃、日本の自然学校のリーダーを中国の関係者に紹介して、中国国内に自然学校のネットワークを作るプロジェクトに取り組まれており、その話を都心まで聞きに行ったとき、お目にかかった記憶がある。
昨年1月、私が企画・コーディネートを務める市民向けの環境講座にヤンヤンさんをゲストに迎え、話題提供していただく機会があった。
新時代アジアピースアカデミーが主催する講座だったので、「アジア」「環境」をキーワードにお話いただけそうな人にお願いしようと思い、ヤンヤンさんに声を掛けてみた。
中国の市民社会について私が知っていることは、以前お目にかかった10年以上前からほとんど変わっていなかったので、この機会に情報をアップデートしたいと考えたのだった。
ところが、ヤンヤンさんは、中国の市民社会や日中間の比較よりも、この約30年ほどの日本の市民社会の推移を踏まえて、最近調査していることや考えていることを話したいとお返事だったので、やや意外な印象を受けた。
そのときの講座のタイトルと概要は以下のとおりであった。
「市民社会の新たな潮流と市民育ちの可能性を問う」
概要:1995年以降の日本における市民社会の思潮を俯瞰すれば、
持続可能な社会に向かおうとする市民的実践の動向も見えてくる。
NPOという新たなタイプの組織を軸とした取り組みから
ソーシャルビジネスに代表される事業を軸とした取り組み、
さらに近年台頭するプロジェクトを軸とする多様な地域での取り組みに至り、
市民社会の「現れ方」が変化している。
この変化の中で若い世代が如何に市民として育つのか。
持続可能な社会を求めるグローバルな運動の変化や、
中国での自然教育ブームなどの話も交えつつ、その場づくりの可能性を問う。
ゲスト出演を依頼したときは、私の守備範囲ではない部分をカバーしていただこうと考えていた。
ところが、お話を実際にうかがってみると、私の問題意識と近いことを私よりも深く考えていらっしゃることがわかり、それまで以上に親しみを覚えた。
その後、ヤンヤンさんから書籍をご恵贈いただいたり、今年4月にあった本書の出版記念セミナーについてご案内いただくなどしたが、これまで何もお応えできていなかったので、今回のコラムで取りあげることにした。
なお、ここでは本書のほかに、長谷川公一編『環境と運動』(2024年、ミネルヴァ書房)に所収の論考「ボトムアップの社会づくりを支える力」の内容も踏まえて、感じたことや考えたことなどを記したい。
まず、本書の優れている点は、先行研究のレビューがしっかりしていること、また、日本のNPO・市民社会の動向の整理が的確であることが挙げられる。
市民社会論やコモンズ論など大量の文献を読み込み、それぞれの著者の関心に即して内在的に理解したうえで、日本の市民社会の動向を示すデータも冷静に分析し、その内容をヤンヤンさん独自の視点で、わかりやすく明解に整理する。
母国語ではない日本語で書かれた図書や論文であっても、その解釈はとても丁寧で深く、また重要な部分については、大胆に図表を用いてまとめている。
だから、日本の市民セクターに関心を持つ人にとっては、非常にありがたいテキストとなっている。
私には、とてもこんな芸当は真似できないので、ヤンヤンさんのこうした学術的なスキルの高さには脱帽するばかりだ。
ただし、私が本書を取りあげたのは、大量のテキストや計量データを高度に処理する能力の高さからではない。
この30年間の市民社会の潮流といっても、どのような視点から読み解くのかによって、解釈には相当の幅が生じるだろう。
たとえば、NPOは社会に根づいた一方で行政の下請け化が進み、市民がフロンティアを切り拓いていくような力が弱まっているとか、市民セクターもほかのセクターと同様に担い手が高齢化して、世代交代が進まないなど、ネガティブ話題に関心が向かいがちである。
しかし、ヤンヤンさんは、私たちの未来を明るく軽やかに語る。
その語り口に説得力を持たせているのが、堅実な文献レビューであり、客観的なデータ分析にある。
本書では、近年の日本における市民セクターの展開を次のように整理する。
(1)1995-2005年:「新しい公共性」が志向された時代
(2)2005-2015年:社会起業とソーシャルイノベーション時代
(3)2015年-:「ソーシャルデザイン」と「セルフデザイン」がシンクロする時代
この時代区分と、別の論考で整理された市民社会論の系譜を対応させ、私なりに整理すると、次のようにまとめられる。
(1)「新しい公共」志向…能動的な主権者としての市民が、行政に独占されていた「公共」に参画する権利を主張するため、政治的機能を表に出す社会運動的な側面が現れやすかった。
(2)課題解決志向…社会課題に対して高い意識を持って行動する市民が、NPOの専門性やマネジメント力を高めて課題解決を図ろうとするため、経済的・福祉的機能が強調され、ソーシャルビジネス的な側面が目立った。
(3)ウェルビーイング志向…豊かな暮らし方を求める生活者が、人びとのつながりと相互承認、共に生きることが実現される領域として市民社会を意味づけるため、社会的・文化的機能が強調され、社会関係資本(ソーシャルキャピタル)的な側面が表現されやすい。
こうした整理は、NPOに当事者として関わってきた私から見ても妥当に思われる。また、(3)の説明は、ありのままでいられる「居場所」が必要とされる今日の社会ニーズをうまくとらえているだろう。
ヤンヤンさんは、市民社会が求める3つの歯車――(1)参加の権利、(2)参加の仕組み、(3)参加の文化――がかみ合うことで、社会が前進していくような図も描いているのだが、これも上記の時系列による整理と対応している。
さて、こうした解釈は、よく整理されていてわかりやすいというだけではなく、市民社会を多元的に捉える必要性を教えてくれる。
たとえば、年配の活動家が、運動的な側面が弱まってきたことを嘆く気持ちはわかるが、私たちはただ力を失ってきたわけではない。
以前よりも、一人ひとりが自分の生活と活動をともに大事にしながら、私たちの間で交わされる言葉を大事にして、他者を収奪せずに共に生きられる社会をつくろうときた面もあるだろう。
そうした活動は、ささやかであるかもしれないが、しっかりと地に足の付いたもので、自分で頑張りすぎないし周りにも無理をさせず、人間としての体温が感じられるものである。
本書でヤンヤンさんは、「自分にとっての義務や経済的利益にとらわれることなく、社会的・公共的な事柄に参加する人々」として市民を定義する。
これは、西欧的な「市民」概念をそのまま輸入するのではなく、社会学者らしく東アジアの市民社会を観察する中から導き出したものだ。
ヤンヤンさんがこのように市民社会を柔軟に捉える背景には、中国のNPO研究の蓄積があるようだ。
中国では、政治的な市民参加を求めても、思うように獲得することは難しい。
この点は、日本社会よりもはるかに厳しい現実がある。
しかし、参加の権利を広げることが困難であっても、中国のNPOは参加の仕組みを活かし、キャンペーンやイベントを開いたり、ソーシャルビジネスを回したりなどして、社会に影響力を与えてきたという。
つまり、政治的な機会構造は開かれていなくても、市民として豊かな社会を実現しようとして活動し、この地球に生きているという点では、中国も日本と変わりがない。
両者の違いにばかり焦点を当てるのではなく、共通したり重なったりする部分に光を見いだし、相互に学び会う方がともに豊かな社会に向かって行くことができる。
ヤンヤンさんは、きっとこんなふうに考えて、日本の市民社会の変化のポジティブな要素に着目しているように思われる。
この視点、そして感性は、たとえ政治体制が違う国同士であっても、市民が交流することによって、よりウェルビーイングな方向へ、持続可能なかたちで切り拓くことができるという信念に支えられているようだ。
しかも、その信念は、根拠のない空想的なものではなく、日中の市民社会研究と市民交流の実践の経験から得られたものだから、納得できる。
本書では、西欧の市民社会論もレビューされているが、そうした借り物の概念を議論の軸にしていない。
日本には(中国でも)、社会的・公共的な事柄に参加する市民がいて、それぞれの地域で積極的に活動している。
だから、ヤンヤンさんは学生と一緒に地域に飛び込み、さまざまな市民と交わる中から、市民として育つようにと願っている。
本書には、学生たちと一緒に調査した結果が数多く含まれているが、そこには大学における市民教育への期待が現れているとも読める。
ヤンヤンさんは、市民が育つ場としての地域を掘り下げていくなかで、幅広いコモンズ論をレビューし、「市民的コモンズ」という概念を生み出した。
この言葉に「市民的」という修飾語が付いているのは、単にコモンズと呼ぶと、人々が地域の山野河海を共同管理してきた伝統的なコモンズをイメージするためであろう。
しかし、私は逆に「市民的」という言葉が、西欧近代的な市民像を喚起してしまうようだろうから、「現代的コモンズ」くらいでよいのではないかと思う。
ともあれ、私も環境社会学のコモンズ論から強い影響を受けて、現代の市民社会について議論してきたので、ヤンヤンさんがコモンズという言葉を重視していることは嬉しく感じられた。
さらに、コモンズという空間・資源それ自体が重要と考えているのではなく、コモンズをつくり、それを絶えず編み直しつづける実践(commoning)のプロセスに関心を向けている点も共通していると思えた。
私の場合、環境社会学を専門にしているといっても、私の関心を寄せる環境とは、人びとが自分を生きる場としての環境であり、他者と共に生きる場としての環境である。
私が思うに、持続可能な豊かな社会へと向か市民が育つ場とは、ヤンヤンさんの言う市民的コモンズであり、そうした場をつくり続けるコモニング(本書では「コモーニング」)が、それぞれの地域の中で豊かに実践されることだと信じている。
本書では、多くの理論的な検討を経て、「市民的コモンズ」を次のように定義しているが、大事なことを言い尽くしている。
具体的な資源を媒介とするコモーニングの過程であり、多様な目的を持った多様な人々が関わり、オープンなコミュニティづくりによってエンクロージャーに抵抗し、市場システムで切り捨てられてきた価値の再構築を行い、自生する社会秩序を志向する協治の仕組みである。
最後に、本書の構成について言及しておく。
多くの章は、すでに書籍や雑誌などで公表された論文がもとになっており、独立して読んでも読み応えがある。
しかし、おそらく本書の構成は、各章のレビューや事例研究に取りかかる前に考えられていたものではないだろう。
市民社会論のレビューがあって、事例研究があって、コモンズ論のレビューがあって、事例研究があってというように、各章の議論が整理されているのと比較すると、あっちへ行ったりこっちへ行ったりという感じが否めない。
それでも、私はそうした議論の進め方を、好意的に受け止めることができた。
移りゆく現代社会を捉えようとするならば、隙がないような全体構想を、前もって描くことは困難である。
調べて考えて、また調べて考えての繰り返しを、飾らずに素直にまとめたのが本書なのではないか。
実際読み通してみると、一直線には行かなかったヤンヤンさんの思索の旅を、後を追っていくような感覚を覚える。
こうした道のりはたどることによって、ヤンヤンさんの学術的な手堅さ、自分に足りない点があることを認め、さまざまな人びとから学ぼうとする謙虚さ、豊かな未来を構想しようとする前向きな姿勢などが、ありありと伝わってくる。
そして何よりも、地域で活動する市民の力と、その中で揉まれて成長していく学生の可能性を信じて前を向くヤンヤンさんの温かい気持ちが感じられる。
本書はバリバリの学術書であるけれど、私は人間愛にあふれた本だと感じた。
市民を中心とした社会づくりに希望を抱きにくい時代にあって、本書のメッセージは私たちを励ましてくれる。
ヤンヤンさん、どうもありがとうございました。
(松村正治)