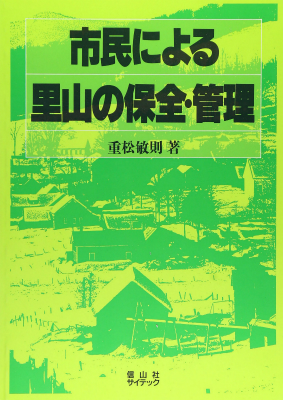第1回と第2回のコラムでは、80年代後半に、里山を守ることの意義が専門家によって見直されたこと、そして90年代後半に、守るべき里山のイメージがメディアを通して一般に広く知られるようになったことを書きました。
しかし、私が里山に対して興味を持ったきっかけは、今回紹介する『市民による里山の保全・管理』でした。
私が大学を卒業後に最初に就職したのは環境コンサルタント会社でした。
入社して間もなく、仕事をする上で先輩はどんな本を読んでいるのだろうかと思い、机に並んでいる本を観察したところ、2冊の本が目に止まりました。
1つは、バイエルン州内務省建設局編『道と小川のビオトープづくり』(集文社、1993年)という本でした。
これは、道路を建設したり河川を整備するときに、そこが生き物にとっても快適な生息空間になるように目指しているドイツの試みを紹介したものでした。
当時は、旧建設省が、ビオトープ、多自然型川づくり、エコロードなどの言葉を用いて、環境に配慮した建設工事をすすめていた時代だったので、この本は格好のテキストとなっていました。
もう1つ私が気になった本が、『市民による里山の保全・管理』でした。
日本では、昭和30年代に燃料革命を迎え、薪炭林・農用林として利用されてきた里山が価値を失い、人と自然とのかかわりが途絶えてしまいました。
人が手を入れていたからこそ生じた明るい林や草地などを棲み処としていた生き物たちは、里山が管理されなくなって急速に数を減らしていました。
こうした里山におけるアンダーユースの問題に対して、法や経済の制度を変えるという大がかりな解決策以外に、市民でもできることがあるのだと教えてくれたのが、この本でした。
里山が経済的な価値を失ったのならば、経済的な価値を求めない市民ボランティアが、里山を管理するというやり方があることを示してくれたのです。
重松氏は、里山が今日のように注目されるずっと前の1975年から、里山林の保全・管理の関する植物生態学的な調査研究を行っていました。
まだ、保全生態学という言葉がなかった頃ですが、大阪府立大の高橋理喜男氏のもとで、当時にあってはユニークな研究を展開していました。
1988年からは、それまでの研究成果を活用するために、市民参加による里山管理について実践的な研究を始めました。
イギリスのBTCVという環境保全団体の活動と組織運営を日本に紹介し、市民ボランティアによる里山保全運動のうねりを作り出しました。
私は、この本を読んで強い影響を受けて以来、市民による里山保全を考えることはライフワークの1つとなっています。
まずは、民間会社を退職して大学院に入り、市民による里山保全を修士論文のテーマにしました。
そして、横浜でフィールドワークを行う中で、今、一緒に活動している仲間達と出会いました。
そうこうするうちに10年以上の年月が流れ、現在に至っています。
この間、市民ボランティアの限界を感じることが多かったのですが、一方で、その可能性の大きさにも、ずっと引き付けられています。
こう振り返ってみると、この本と出会わなかったら、今とは異なる人生を歩んでいたのかもしれません。
なお、同じ著者の重松敏則『新しい里山再生法-市民参加型の提案』(全国林業改良普及協会、1999年)では、『市民による里山の保全・管理』よりも情報が新しくなっています。また、石井実・植田邦彦・重松敏則『里山の自然をまもる』(築地書館、1993年)にも、短くエッセンスが書かれています。