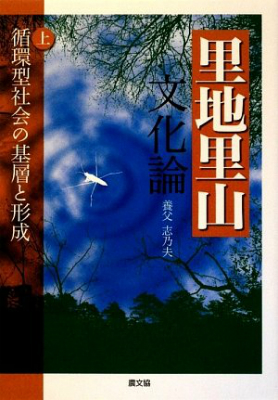これまで、このコラムでは、刊行されてしばらく経った本ばかりを取り上げてきましたが、たまには新刊本も扱いましょう。
今年の9月に出た上下2冊約450ページの本です。
平易に書かれているので、興味があれば、読み通せると思います。
著者の養父さんとは、かつて会社員時代に、何度か仕事でお世話になったことがあります。
私は、環境コンサルタントの会社に勤めており、国、地方自治体、外郭団体、大手ゼネコンなどから委託されて、環境アセスメントをおこなったり、行政計画を立案したりしていました。
東京に本社を置くコンサルでしたが、八幡平、秩父、飛騨、阿蘇、屋久島などの地方へ、自然豊かな地域へと出張に行くことが多かったです。
当時、もう15年ほど前ですが、働きながら考えていたのは、東京のコンサルが地方へ出かけて仕事をするよりも、その地域に根ざした会社やNPOがあれば、そちらに仕事を任せた方が良いはずだということでした。
そうすれば、仕事を通して得られる知識や経験が、その地域の人に残るからです。
短期的には成果が出ないかもしれないけれど、長い眼で見れば、その方が良いと思いました。
大学を出たばかりの当時の私のような若僧が、地方の実情も知らずに調査して報告書を書き、それがほとんどそのまま成果となってしまうことに
違和感を覚えていたのです。
だから、退職後に、地域の実情をよく知るNPO・市民団体と出会い、そこに可能性を見つけてきたわけですが、コンサル時代の半分の給与を得るにも苦労するありさまです。きちんと稼げる仕事にしないといけないのですが・・・。
この方向で考察を深めていっても、明るい見通しがあるわけではないので、話を元に戻します。
養父さんには、エコロード(調査・計画段階から設計・施工・管理の段階まで、自然環境の保全に配慮された道路)関連の仕事で、学識者としてのアドバイスをいただくことが数回ありました。
私が担当した仕事では、学識者で構成される委員会を設置し、コンサルがまとめたレポートをもとに、議論してもらうことが一般的でした。
だから、大学の先生をはじめ、多くの学識者と仕事をしましたが、その中で養父さんはもっとも印象に残っている方の1人です。
理由は、きわめて実際的なコメントをされるからでした。
たとえば、新しい道路を作ろうとすると、貴重な魚や昆虫等が生息する池を埋める必要があるとします。
エコロード設計に基本的な考え方としては、なるべく道路の位置がその池にかからないようにするなどの対応を考えるのですが、地形や予算等の条件によっては、池を埋めざるをえないこともあります。
その場合、代償措置として、近くに新たな池を作ることになります。
しかし、どうすれば、その池に元いた希少な生きものを呼び込むことができるのでしょうか?
この難題に対して、池の深さを○cmにするとよい、水路の落差を○cm以内にしないといけない、というように、コメントは実に具体的でした。
ここまで踏み込んで言えてしまうことに、私は驚きました。
私が働いていた会社では、調査、計画、設計と、部署がそれぞれ分かれていました。
調査系の人が、植物、動物、土壌などを調べ、次に計画系の人が、その調査結果に基づいて、自然環境に配慮した大枠の計画を立て、最後に、設計系の人が具体的に図面を引いて何かを作り出す。
これが、理想的な仕事の進め方だったのでしょうが、このように役割分担しているので、調査・計画・設計をすべて見通せる人は皆無でした。
それまでの学校教育では、生き物を含めた環境デザインのできる人材は育てていなかったのです。
しかし、養父さんは、生き物のことがわかって図面も引けてしまうので、当時にあっては希有な存在でした。
エコロジカル・デザイン、ビオトープ、エコロード、エコパークなど、生き物に配慮した計画設計が求められていたので、養父さんはあちこちから引っ張りだこで、連絡を取ることが難しい方でもありました。
私が養父さんを尊敬しているのは、自然環境の保全・修復技術を開発し、施工実験を通じて検証を行い、保全工法の体系化を進めてきたことです。
国内で未開拓だった分野に果敢に挑戦されてきた成果は、『自然生態修復工学入門』『ホームビオトープ入門』、『田んぼビオトープ入門』『ビオトープ再生技術入門』などの著書にあらわれています。
一方、自然や生き物を対象とした研究者として、本当にそこまで言ってしまっていいのだろうか、と思うことまで断言されることに、私のスタンスとの違いを感じていたのも事実です。
もちろん、実際の施工現場では、詳細な設計図面が必要であり、そのためには、具体的な数値を示すことが求められ、それに養父さんはよく応えていたと思います。
しかし、一緒に仕事をしながら、やはり割り切れないものを感じていました。
今回、上梓された『里地里山文化論(上・下)』は、読後に、その部分をあらためて感じました。
特に、上巻「2章 「里地里山文化」形成史」と4章 日本列島の暮らしと自然を支えた里地里山文化」では、日本文化の基層は、ヒトが生かされヒトが育んできた里地里山文化であると主張しているのですが、かなり強引に結論づけている印象を覚えました。
そもそも、日本や里山を一括りにして語ることは無理でしょう。日本も多様だし、里山も多様です。
私は、仕事を通して養父さんから、ディテールにこだわる大切さを学んだつもりなのですが、それなのに、なぜこんなにも大それた議論を展開したのだろうというのが正直な感想です。
この本の中では、上巻の「1章 里地里山とは何か」と下巻の「1章 昭和20~30年代までの里地里山の暮らしとその変貌」は、最近の研究がよくまとまって書かれています。
上巻の「3章 里地里山文化の源流」と下巻の「2章 伝統的技術による里地里山の修復と生態系の再生」は、それぞれ、中国・韓国と日本の事例のレポートです。
この上下巻の章立てには論理性が欠けており、農文協の仕事にしては質の高さが感じられませんでした。
哲学者の内山節さんが、「本書によって「里地里山」は懐かしさから、これからの自然と人間の関係を探るための指標に変わった」と推薦文を書かれていますが、私からすれば、「懐かしさ」に正統性を与えようとして無理が生じている本だと思います。
いつも温厚なコラムにしては、今回は少し辛口になりました。
これも、私が養父さん、内山さん、そして、農文協の本の愛読者だからですので、ご海容ください。