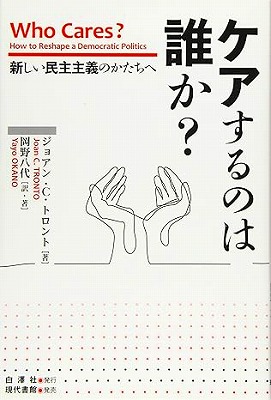ジョアン・C・トロント『ケアするのは誰か?:新しい民主主義のかたちへ』(2020年、白澤社)
本書は、フェミニズム政治理論を専門とするトロントの講演録である。
比較的薄い本なので、重厚な議論を期待する向きには物足りないかもしれない。
しかし、本書の魅力は、この「問い」(英語ではwho`s care?)に対する著者の考えよりもむしろ、この問いそのものだと思う。
社会のいたるところで「ケアをするのは誰か?」と問いかけてみると、そのように問う以前と比べ、景色が違って見えるようになるだろう。
本書では、家事や医療や介護などのケアの多くを女性たちが引き受けていること、その役割分担を当然のように受け止めている社会のあり方が政治的な問題として指摘される。
この社会を維持するために不可欠なケアは、この社会を構成する人びとの間で、いびつなかたちで分担されている。
しかし、そこに疑問を感じることは少なく、政治的なテーマとして扱われずに放置されてきた。
本書が掲げる問いには、このケアをめぐって隠されてきた問題性を引きずり出し、社会の見え方を変えてしまう破壊力がある。
もっとも、ケアをめぐる問題はジェンダーバランスだけに留まらない。
私たちが生きる環境、自然のことまで、ケアする対象を広げて考えてみると、それを担っているのが農山漁村、一次産業の従事者に偏っていること。
さらに、そうした分担を当然のこととして見なしていることも、ジェンダーと同様に問題ではないだろうか。
つまり、ケアという言葉には、さまざまなテーマを横断的に扱える可能性がありそうだ。
そこで今回は、私が普段気になっていることや取り組んでいることとケアとの関連について、思索を深めてみたい。
少し前に、真田純子『風景をつくるごはん:都市と農村の真に幸せな関係とは』(2023年、農文協)を読んだ。この本は、「なぜ地方の人たち、とりわけ中山間地の人たちばかりがんばらなくてはならないのか?」という素朴な問題意識から書かれている。
農山漁村では、農家民宿、ご当地グルメ、ゆるキャラ、二拠点居住、ワーケーションなど、都市から人を呼び込み、お金を落としてもらうために、趣向を凝らした地域づくりがおこなわれている。政府による地域振興策に後押しもあって、現在では、都市の資源をいかに地元へ取り込むのかをめぐり、地域間で先進的な取り組みを競い合っている。
また、地方には課題が山積しており、その解決に向けた取り組みが必要だからと、若者やクリエーターに焦点を定めて、地方でこそ創造性を発揮できる、というふれこみもあふれている。
もちろん、そうした取り組みの中には良い事例が見られるし、競争的な環境が地方活性化を促すことも否定しない。しかし、私には地方同士がパイを取り合っている状況を、都市側からスポーツ観戦のように、その展開を眺めて楽しんでいるだけのようにも見える。
そこで、少子高齢化・人口減少、鳥獣被害の増加など、今日の地方が直面している問題は、地方の問題なのだろうか、と問うてみたい。これまで続けてきた田畑、里山に手を入れることができず、放棄されているのは、地方だけが取り組むべき課題なのだろうか。
私はそうではないと思っている。
私は法政大学で「都市の環境問題」という授業を非常勤で担当している。
この授業科目について「都市の環境問題とは?」と生成AIに聞いてみると、人間活動の集中と自然との乖離がもたらすので、大気汚染、水質汚濁、廃棄物問題、騒音振動、ヒートアイランド現象、自然環境の喪失が挙げられる。
たしかに妥当な答えだが、これは都市という領域の中で生じる問題である。
私は都市について考えるとき、都市領域を対象とするだけでは不十分だと考えている。
都市は、その中で生きる人びとにとって不可欠な食やエネルギー、グリーンインフラなどを、外部に依存しているところに特徴がある。
ある都市史の専門家は、「都市とは、都市だけでは成り立たない存在」と定義しているが(→林憲吾|コラム「都市とは何か?」)、この説明は適当だと思う。
歴史的に見れば、都市は農村と機能が分化されて生まれたものであり、両者の関係性について射程に入れなければ、都市を考えることにならない。日本では、高度成長期に地方の農村から都市へ人口が大量に移動したので、多くの都市住民は地方出身者であった。
彼/彼女たちは、同時代の日本の中で生活世界が大きく異なる都市と農村を比較し、両者の間に横たわる不公平感や出身地を離れたことへの後ろめたさなどを抱き、都市に住みながらも地方について気に掛けていた人が多いように思われる。
しかし、人口移動も落ち着き、農村で暮らした経験のない都市住民が多くなると、都市が食やエネルギーなどを地方の農村(場合によっては外国)に依存するのは、都市が農村よりも強くて稼げるために市場原理から自然と決まってくるもので、両者に見られる力関係は当然のことと受け止められるようになったのではないか。
このため、過疎高齢化、耕作放棄地の増大、獣害問題、インフラ老朽化など、地方の農村に典型的に見られる問題は、都市とは無関係な問題として受け止められ、農村が自力で解決することが当然とみなされやすくなっている。
私はこの問題こそが、「都市の環境問題」の核心だと考えている。
つまり、都市住民の暮らしを支える地方の農村における風景について、考えなくても済むと思っていることが重要な問題だと認識している。
藤田弘夫『都市の論理:権力はなぜ都市を必要とするか』(中公新書、1993年)は、都市と農村の間の権力関係に力点が置かれた都市論の名著だが、都市を考える上で、両者の関係性を見るような視点は希薄になっていると思う。
2011年の福島原発事故は都市生活の基盤が非常に脆弱であることを突きつけ、多くの首都圏の住民が「都市の環境問題」に気づくきっかけとなったけれど、14年の月日が経過して、事故前の常識が戻ってきたような気がする。
このような自然や風景のケアをめぐる都市と農村の不公平な関係について、都市の側からも考えるべき問題としてとらえると、人間のケアをめぐるジェンダー間の不公平な関係を厳しく指摘するトロントの議論とも接続できそうだ。
すると、たとえば、都市住民は農村環境から得られる食やエネルギー、グリーンインフラなどを搾取するばかりで、その生産や維持に必要なケアを無視しているから、農村が過剰に負担している自然のケアを都市側も分担して、都市と農村が対等で公平な関係をつくろうと言いたくなるだろう。
しかし、そのようなメッセージを私は好まない。
なぜなら、自然のケアは単純な負担やコストではないと思うからである。
むしろ、現代を生きる私たちにとって、自然をケアすることから得られる気づきや学びは、これからの社会をつくるうえで大事だと信じているからである。
ここで、家事や医療や介護などのケアと、自然や風景のケアの共通項として、ノイズを扱うということがある。
どちらも自分の思うようにコントロールすることはできないが、ただ、その他者性におろおろするばかりではなく、相手の反応を見ながら、できることを試行錯誤する。
うまくいかないことに悩みながらも、ふりかえってみれば、何も対処しなかったよりよい結果が生まれ、自分を見つめ直していろいろと考えたことで
自らの成長にもつながったと実感できることが多い。
今日の社会が抱える課題は、欧米社会に答えがあって、それを速やかに導入して定着させれば解決できるようなものではない。
答えのない問題群を前にして、私たちは前向きに取り組もうという意思を持ち、成功だけではなく失敗からも学ぶ力によって、少しでもましな社会をつくっていくことが求められる。
そのような社会では、ノイズに満ちた他者をケアすることから培われる力が、必要とされていると思う。
ただし、先行きが不透明な現代社会を生き抜くために、他者のケアを通して学ぼうと呼びかけるのも、違和感を覚える。
私が、里山保全のボランティア活動に関わっているのは、実践を重ねることで自分の成長が感じられることが、それがカタツムリのように遅くても、楽しいからである。
ケアの中には、確実に楽しさがあるはずだ。
それは、人間が自然の恵みをいただき、災いを避けながら生きる存在であり、また、人間がケアしたりケアされたりする人の間に生きる存在であるのだから、そこに楽しさがなければ、人間の存在自体を歓ぶことができないだろう。
私は、人間として生きていることを確かなものにするためにも、ケアは人間にとって根源的に重要なおこないだと思う。
だから、ケアから逃げるのではなく、ケアとうまく付き合いたい。
もちろん、自己犠牲によって自分を失うほど他者をケアしてしまうのは不健全だし、ジェンダー間、都市と農村の間の不公平な関係は是正すべきである。
そのことを確認したうえで、私はケアすることで人間でありたい。